2007/03/07 Wednesday
2007/03/17(Sat)
 ブログでWordpressを使って、海外のthemesのデザインを使うと、スタイルシートが英語文字用に、設計されているために、それに日本語文字を書き込んだ場合、表示される文字が、日本語の場合は、著しく小さく表示されてしまうことがある。
ブログでWordpressを使って、海外のthemesのデザインを使うと、スタイルシートが英語文字用に、設計されているために、それに日本語文字を書き込んだ場合、表示される文字が、日本語の場合は、著しく小さく表示されてしまうことがある。
こんな場合は、そのthemesのファイルの中に入っている「style.php」を、開いて、その中の『content』(ここの部分は、制作者が何人であるかによって、変わってくる。たとえば、制作者がドイツ人である場合には、ここの部分は「inhalt」と書いてあるはずだ。)という文字を検索で探し、その横にある「font-size: 1.2em;」などと表示されている数値を、たとえば「1.5em;」などに書き直し、上書きして、その「style.php」分だけをアップロードしなおせば、かなり見やすくなるはずだ。
もっとも、この「content」の部分は、通常、ブロックに分けられていて、そのブロックごとにfont-sizeが指定されているので、一部ブロックのfont-sizeだけを直すと、画面のバランスが悪くなってしまう。
もし、これまでの各ブロックごとの文字バランスをそのままに、大きな文字で、という場合には、最初の段の方にある「body」の部分に、「font=**.*%」と書いてある部分があるので、この数値を、たとえば、これまで、「62.5%」と、書いてあったら、これを「90.5%」などと、修正すると、「content」の各部分の指定文字が、そろって、均等の比率で拡大することができる。
また、ついでに、その横にある「line-height」の数値も、たとえば「line-height: 150%;」と書いてあったら、「line-height: 160%;」などと修正しておくといい。
なぜなら、英文字と違って、日本語のフォントの場合には、高さが要求されるからだ。
また、新しいWordpressバージョンME2.1.2 にかえると、それまで投稿画面についていた「クイックタグ」欄がなくなっていて、記事中にハイパーリンクをつけるのが、非常に面倒になる。
この場合は、「Auto-hyperlink URLs」というプラグインをダウンロードし、ファイル「plugin」に入れて、アップロードした後、、管理画面の「プラグイン」をクリックして、「Auto-hyperlink URLs」と、表示されている右横の「有効化」をクリックすれば、URLが記事中で、そのまま、ハイパーリンクに変わってくる。
为翻译对汉语, 使用这
⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
⇒http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-掲示板-ご意見
2007/03/04 Sunday
2007/03/04(Sun)
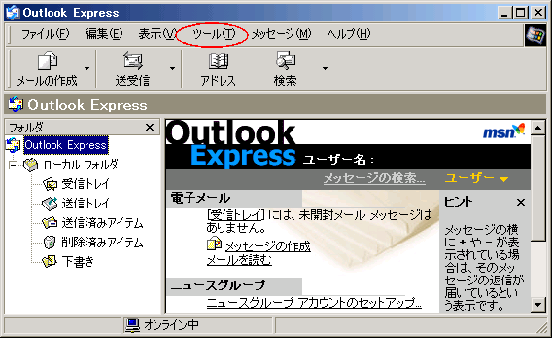 使っているメールソフトOutlook Expressで、ある日、受信ができても、送信ができなくなる場合がある。
使っているメールソフトOutlook Expressで、ある日、受信ができても、送信ができなくなる場合がある。
エラー番号:0×800CCC0F
または
エラー番号:0×800CCC78
が出てくる。
その場合の対処法だが
サイトで調べてみて、次のように対処したら、私の場合は、解決しました。
どうも、原因はダウンロードされたOutlook Expressのデフォルトの設定値にあるようで、
ツール→アカウント→「対象メールアドレス」クリック→「プロパティ」クリック→「詳細設定」クリック→「送信メール(SMTP)」が、デフォルト既定値「25」となっているのを「587」に変える。→「サーバー」クリック→「送信メールサーバー」の「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れる→『OK』クリック→再起動→
これでOKのようだ。
原因は、プロバイダーが、迷惑メール送信対策の一環として、次のような設定を、故意にしていることにある。
つまり、
「Outbound Port 25 Blocking(OP25B)はインターネットサービスプロバイダの悪意ある顧客が自前のサーバからスパムを送信したり、SMTP拡大型のウイルスに感染したPCからウイルスメールが送信されることなどを防止するために、インターネットサービスプロバイダ側で許可した特定のサーバ以外のSMTP(TCPポートの25番)の送信をブロックするという対策方法である。」
サーバーを変えたりした直後などは、この点、注意のようだ。
逆に言えば、TCPポートの25番で支障ないサーバーは、ダメサーバということになりそうだ。
为翻译对汉语, 使用这
⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
⇒http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-掲示板-ご意見
2006/10/31 Tuesday
2006/10/31(Tue)
 おそらく、皆さん方のお宅でも、家中にコンピュータが増えて、インターネットが、競合して、つながらなく場合が、よくあることだとおもいます。
おそらく、皆さん方のお宅でも、家中にコンピュータが増えて、インターネットが、競合して、つながらなく場合が、よくあることだとおもいます。
私の場合も、6台、おまけに、隣接家屋かららしき電波も入ってきているようです。
その場合の対処方法を以下に整理してみました。(Windows XPの場合についてのみ記載)
1.『 「Windowsシステムエラー ネットワーク上の別のシステムと競合するIPアドレスがあります」 』とのエラーメッセージが出る場合
 .
.
.
.
.
対処方法
『スタート』クリック→
『すべてのプログラム』クリック→
『アクセサリ』の中の『コマンドプロンプト』クリック→
『ipconfig/release』と入力→
『Enter』→
『ipconfig/renwew』と入力→
『Enter』→
『exit』と入力→
『Enter』
2.ネットワークの状態に黄色い!(感嘆符)マークが出て、『接続状態: 限定または接続なし』とのエラーメッセージが出る場合
 .
.
.
.
.
対処方法
『スタート』クリック→
『コントロールパネル』クリック→
『ネットワーク接続』クリック→
『ワイアレスネットワーク接続』のアイコンを右クリック→
『プロパティ』クリック→
『全般』タブをクリック→
『□接続が限られるか、利用不可能な場合に、通知する(M)』の□内のチェックをはずす→
『OK』をクリック
为翻译对汉语, 使用这
⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
⇒http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-掲示板-ご意見
2006/10/14 Saturday
2006/10/14(Sat)
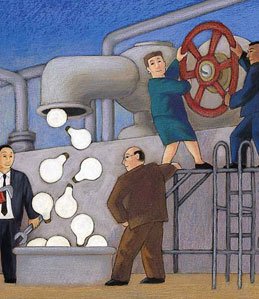 このサイト「イノベーションとは?」によれば、1958年の経済白書で、「イノベーション」を「技術革新」と、誤訳してから、日本のイノベーション感覚は、くるってしまったと、指摘している。
このサイト「イノベーションとは?」によれば、1958年の経済白書で、「イノベーション」を「技術革新」と、誤訳してから、日本のイノベーション感覚は、くるってしまったと、指摘している。
(注-「経済白書データベース」で検索する限りて゜は、経済白書にはじめて、「イノベーション(技術革新)」との記載があったのは、1958年(昭和33年)ではなくて、その二年前の1956年(昭和31年)の経済白書である。このサイトの末尾記載の参考資料ご参照)
すなわち、このサイトの早稲田大学の吉川智教氏によれば、どんなに優秀な技術を開発したところで、その技術を取り巻く社会的環境や、川下のマーケットにいたる諸条件がととのわなければ、その技術革新は、生きてこない、といわれている。
そこで、肝心の唱える安倍さんが、このイノベーションをどう解釈しているかなのだが、施政方針を見る限りでは、次のとおりである。
「人口減少の局面でも、経済成長は可能です。
イノベーションの力とオープンな姿勢により、日本経済に新たな活力を取り入れます。
成長に貢献するイノベーションの創造に向け、医薬、工学、情報技術などの分野ごとに、2025(平成37)年までを視野に入れた、長期の戦略指針「イノベーション25」を取りまとめ、実行します。自宅での仕事を可能にするテレワーク人口の倍増を目指すなど、世界最高水準の高速インターネット基盤を戦略的にフル活用し、生産性を大幅に向上させます。」
つまり、「技術革新をテコに成長戦略を推進する2025年までの長期戦略指針」なんだそうですが、ちょっと、微妙ですね。
そこで、このWikipediaの「Innovation」を見ると、世界のイノベーションの概念の変遷がわかって面白い。
これによれば、
1934年にシュンペーターが定義づけた古典的なイノベーションでは、生産過程に、新しい方法や、デバイスを組み込むことによって、新しい方向を生み出すものとしてきたが、
1995年になって、OECDが、「Oslo Manual」(THE MEASUREMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES)で、新しいイノベーションの概念を規定し、Technological product and process (TPP)イノベーションと名づけ、このTPPは、科学的、技術的、組織的、機能的、商業活動的なものを包括するものであると、定義づけた。
そして、今日的な定義では、次のようなイノベーションがあるという。
1.ビジネスモデルとしてのイノベーション
2.マーケティングとしてのイノベーション
3.組織変革としてのイノベーション
4.生産・流通過程でのイノベーション
5.製品イノベーション
6.サービスイノベーション
7.サプライチェーン・イノベーション
8.エンド・ユーザー・イノベーション
そしてそのためには、
1.品質の改善
2.新市場の創造
3.プロダクト・レンジの拡張
4.労働コストの低減
5.生産過程の改善
6.原料の低減化
7.環境負荷の低減
8.生産・サービスの置換
9.エネルギー消費の低減化
10.規制のConformance化
そして、最後に、イノベーションが失敗する要素としては、次のような要素があるという。
1.リーダーシップの欠如
2.組織力の弱体
3.コミュニケーションの貧困
4.劣悪な環境
5.ナレッジマネジメントの弱体ぶり
6.ゴール設定の弱さ
7.ゴールまでの連帯の欠如
8.チームへの参加力の欠如
9.結果についてのモニター欠如
10.コミュニケーションと、情報アクセスの欠如
以上
参考資料
1956年(昭和31年)の経済白書における「イノベーション」についての記述箇所抜粋
技術革新と世界景気
しかし労働生産性を上げるということは単に勤労者が勤労意欲を振いおこすということではない。
近代工業における生産性の上昇には設備の近代化、技術投資が先行しなければならない。
そして年々巨額な投資を推進しているものは、技術の絶えざる進歩とそれを媒介にした企業の競争である。
技術が絶えず進歩しているときに、生産設備を物理的に使用に耐えるまで耐久年限いっぱいに使っているようなことでは、競争会社に圧倒されてしまう。
耐久年限の短縮と取り替え需要は投資財市場を拡大する。1956年の米国の産業設備投資は対前年2〜3割の増加が予想されているが、その半ばまでは近代化の投資である。
長期にわたる近代化投資を予想されている業種のなかに、目先き売れ行き不振で滞貨に悩む自動車産業が含まれていることは、近代化投資需要が目前の好不況の波を超越した強い力をもっていることを示すであろう。
このような投資活動の原動力となる技術の進歩とは原子力の平和的利用とオートメイションによって代表される技術革新(イノベーション)である。
技術の革新によって景気の長期的上昇の趨勢がもたらされるということは、既に歴史的な先例がある。
その第一回は、蒸気機関の発明による第1次産業革命後の情勢であって、1788年から1815年まで長期的に世界景気の上昇が続いた。
第二回目は、鉄道の普及によって1843年から1873年まで、第三回目は、電気、化学、自動車、航空機等の出現に伴って1897年から1920年まで、革新ブームが現出した。
そして現代の世界を原子力とオートメイションによって代表される第4回の革新ブームの時期とみることもできるであろう。
しかし過去の例によってみれば、技術革新ブームによる景気の長期的上昇の趨勢のうちにあっても、景気の後退が発生しないという保障はない。
ただ上昇趨勢中の後退は小幅かつ短期間であったことに注意を要するであろう。
世界景気の現状を仔細に検討するならば、今まで一本調子の登り坂を続けてきた先進国の景気情勢に若干の変調があることがうかがわれる。
アメリカ景気の伸び悩みは自動車、住宅等に対する購買力の停滞をその主因としているが、イギリスは内需増大による国際収支の悪化に、そして大陸諸国は労働力を初めとする生産力の限界に突き当たり、デイスインフレ政策が日程に上っている。
もちろんアメリカにおいても基調としては技術革新ブームによる旺盛な投資需要が存在し、各国ともその経済動向がインフレとデフレの微妙なバランスのうえにかかっているだけに、ブームの背骨を折らずに如何にして調整過程を短期に切り抜けるかは、各国経済政策当局者の苦心の存するところであろう。
いずれにせよ1956年の世界景気は前年ほどの上昇テンポを維持することはできない。
中略
従って成長率の維持のためには、有効需要を経済循環のなかから生みだしながら、同時に将来の生産力を培う課題が要求される。
前に世界経済について述べたとき、技術革新(イノベーション)が高い成長率維持の根因になっていることを説明した。技術革新とはいうけれど、それは既にみたように、消費構造の変化まで含めた幅の広い過程である。
外国では技術革新をさらに拡張して、技術の進歩と、これに基づく内外の有効需要の構造変化に適応するように自国の経済構造を改編する過程を、トランスフォーメーションと呼んでいる。
その内容として普通に挙げられているのは、技術の進歩による生産方式の高度化、原材料と最終製品の間の投入−−産出関係の変更、新製品の発展と消費の型のサービスおよび耐久消費財への移行、国内産業構造の高度化と結びついた貿易構造の変化、生産性の低い職場から高い職場への労働力の再配置などである。さらに最近では新しい世界情勢への適応として、後進国開発援助の動向などもこのなかに含めて考えられるであろう。
我々はこのトランスフォーメーションを経済構造の近代化と名づけることにしよう。
中略
安定的発展のための経営対策
設備近代化と操業度安定
企業経営の発展のための基軸は、生産技術と設備の近代化である。
これまで述べたような30年度における経営の好転が世界的なイノベーション・ブームの波によってもたらされたことを思えば、我が国の企業が次の発展をはかるためには、当然に国際市場で通用するだけの技術革新のための投資を用意しなければならない。
しかしまた同時に生産設備の効率的運用と高能率な操業度の維持に対して、考慮を払うことも同程度に重要である。
我が国の企業の通弊として、景気変動のなかで操業度は非常な不安定な起伏を示し、何年に一度の好況時には操業度が上昇して老朽化設備までもかりだされることがあっても、平常時の生産設備はかなり低操業のままに置かれてきた。
今後の企業にとっては資本効率をできるだけ高めながら近代化投資を進めていくことが、特に必要な課題であろう。我が国の企業が陳腐化設備を温存しながら当面の好況に対処するというのみならば、いつまでたっても世界の限界供給者的な範域から抜けでることはできないであろう。
老朽化、陳腐化設備を廃却しながら設備の近代化に努め、高能率精鋭設備の操業度を高めていくような配慮がなされねばならない。
また近代化設備の操業安定は、単なる生産工程だけの問題ではなく、絶えずマーケット・リサーチ、流通販売面の整備を前提としなければならないこともいうまでもない。
中略
かかる発展の機動力となるべきものが近代化投資であることはいうまでもないが、今後の近代化投資は日本経済の構造変動を可能にするところの投資であり、かつ世界経済の構造変動に適応するところの投資でなければならないはずだ。
その意味において近代化投資の基軸になる産業は、化学、機械であろう。
欧米先進国の産業構造は化学、機械の比重が高いが、さらにイノベーションの主体もこれら産業にある。
我が国の産業構造は戦時生産の遺産によって比重こそ重化学工業化したが、いまだ産業の基軸と呼ぶほどのものではない。輸出にしても、戦前の繊維中心から鉄鋼などへ比重が移行しているが、機械はまだ輸出額の12%に過ぎず、先進諸国の30%以上というのに比べると、我が国の機械産業の遅れが目立つ。
また、いわゆる合理化投資期においても機械産業への投資は立ち遅れていた。
化学は石油化学などにみるごとく新産業的色彩が強く、かつ新しい基礎財産業となりつつある。戦後の技術の発展はめざましかったが、海外技術の導入に終っており、先進諸国の技術は日進月歩の勢いであるから、今日採用した技術が明日にも陳腐化する惧れさえある
以上抜粋終わり
为翻译对汉语, 使用这
⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
⇒http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-掲示板-ご意見
2006/08/19 Saturday
2006/08/19(Sat)
 靖国神社問題に絡んで、一部に「日本にも、アメリカなどのような無名戦士の墓を」なんて声があるのですが。
靖国神社問題に絡んで、一部に「日本にも、アメリカなどのような無名戦士の墓を」なんて声があるのですが。
ちょっと、待ってくださいよね。
ここで、ちょっと、アメリカの「無名戦士の墓」の歴史くらい、頭に入れといてくださいってこと。
で、アメリカのアーリントン国立墓地の一角にある「無名戦士の墓」は、もともとは、1921年3月4日に、アメリカ議会が、無名戦士の墓の設置を決議し、1921年11月11日に、一つの戦争ごとに一体を埋葬することを目的とし、4人の戦士の中から、一人のフランスで殺された身元不確認の戦士が選ばれ、埋葬され、1932年11月11日に、正式に、無名戦士の墓として、専用が決まったもののようで。
「TOMB OF THE UNKNOWN SOLDIER」参照
その後、1958年の戦死将兵記念日に、二つの戦士が埋葬され、そのひとつは、第二次世界大戦で死んだ方で、もうひとつは、朝鮮戦争で死んだ方であったということ。
そして、その時点で、それまでの『the Tomb of the Unknown Soldier』が『the Tomb of the Unknowns』に改められたということ。
ですから、正式には、「無名の方の墓」ということになりますね。
あるいは、「known but to God」(神のみぞ、その名を知る。)とも、いわれていますね。
その後、1984年に、ヴェトナム戦争でなくなった方が埋葬されたのだが、それらの戦士のかたは、その後、身元が分かったので、この墓からは、取り除かれたということらしい。
その後あたりから、DNA鑑定技術が進歩してきて、これ以上の、無名戦士の発生する可能性がないこととなったので、1999年に、アメリカ国防省は、これ以上、この『the Tomb of the Unknowns』に埋葬される方はいないと発表したそうな。
で、その他の国の、「無名戦士の墓」としては、イギリス・ロンドンの「Westminster Abbey」(1920年)や、フランス・パリの「the Arc de Triomphe 」(1921年)、そして、バグダッド(1982年)、ロシアの無名戦士の墓などがあるようだ。
 世界の最初の無名戦士の墓は、デンマークの「Landsoldaten」だそうで、これは、1849年に建てられたそうな。
世界の最初の無名戦士の墓は、デンマークの「Landsoldaten」だそうで、これは、1849年に建てられたそうな。
こちらのサイト「Tomb of the Unknown Soldier」に、各国の「無名戦士の墓」状況が書かれている。
日本の一部に、アメリカの無名戦士の墓は、「無名性により全戦没者を代表させている」なんておっしゃる方がおられるようだが、実際は、そうでなく、本当の意味での無名の墓で、名前が分かれば、そこから取り除かれる類の墓でもあるようだ。
となると、日本には、本当の意味での「無名戦士の墓」と言うものは、ないようなのだが。
ちなみに、東京・千鳥ケ淵墓苑は、名前の特定できない戦没者の遺骨を納める国立の無宗教の墓苑ではあるが、それが、戦士なのか、どうなのかは、特定できていないし、また、アメリカのような、一戦争を代表する戦士の墓ではなく、いわば、合葬による弔いの仕方を取っている。。
参考 千鳥ヶ淵戦没者墓苑のいきさつ
「靖国神社と千鳥ヶ淵戦没者墓苑」より引用
発端
◇厚生省の役所の中には、支那事変以来遺族の判らない遺骨が仮安置されていたが、昭和二十五年一月九日、比島の戦没者四千八百二十二柱の遺骨が米軍により送還されたのを契機に、国で墓を作って納骨しようとの考えが強まった。
二十八年九月二十六日
◇厚生省、文部省、内閣法制局が合同会議を開き、戦没者の墓を国において造営する場合の問題点(特に憲法上)について検討した、結果は「支障なし」との結論であった。
二十八年十月六日
◇厚生省は遺骨問題に関連の深い団体を招き、国で墓を作ることについて意見を聞いた。結果は全団体賛成であったが、一番関係の深い靖国神社が招かれていないことが指摘され、靖国神社の意向を聞く必要が述べられた。
二十八年十一月十八日
◇前項に記した関連団体の第二回会合が開かれ、今度は靖国神社からも池田権宮司が出席した。
池田権宮司は次の点を厚生省援護局長に質した。
問 墓苑は引取り遺族の判らない遺骨を納めるために作られるのだが、これを全体の象徴的墓とするようなことになると、靖国神社と重複することになって将来具合が悪いのではないか。
答 全体の象徴とする考えはない。
問 名称が「無名戦没者の墓」となるようだが、これは国民にアメリカのアーリントン墓地を連想させ、全戦没者を代表する墓という印象を与えるのではないか。
しかもそれが国立の墓地であるから、現在私法人となっている靖国神社に代るものというような、国民の誤解を招く恐れはないか。
答 名称は未だ仮称だから、今後充分に考慮して決定する。
問 墓は宗教施設ではないのか。これを国で作ることは憲法に抵触しないか。
答 墓は宗教施設ではない。その証拠に所管が違う。(墓は厚生省、宗教施設は文部省)
以上のような経過があった後、昭和二十八年十二月十一日、厚生大臣より「無名戦没者の墓」に関する件が閣議に報告され、閣議で決定された。
記 「無名戦没者の墓」に関する件
太平洋戦争による海外戦没者の遺骨の収集については、関係国の了解を得られる地域より逐次実施しているが、これらの、政府によって収骨する遺骨及び現に行政機関において仮安置中の戦没者の遺骨であって遺族に引き渡すことができないものの納骨等については、おおむね下により行なうこととする。
遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納めるため、国は、「無名戦没者の墓」(仮称、以下「墓」という)を建立する。
「墓」に納める遺骨は、政府において収骨する戦没者の遺骨及び現に行政機関において仮安置中の遺骨であって、遺族に引き渡すことのできないものとする。
「墓」の規模構造については、関係方面の意見を徴したうえ所要経費とともに別途決定するものとする。
「墓」の維持管理は、国の責任において行なうものとする
以上
『Unknown Soldier, Tomb of the』参照
为翻译对汉语, 使用这
⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
⇒http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/08/02 Wednesday
2006/08/02(Wed)
 昨日、国税庁から2006年の全国の路線化が公表されたが、ここにも、日本列島各県の勝ち組・負け組みの差がくっきり現れている。
昨日、国税庁から2006年の全国の路線化が公表されたが、ここにも、日本列島各県の勝ち組・負け組みの差がくっきり現れている。
ちなみに、わが秋田県は、日本列島どん詰まりの負け組みであった。
以下は、2006/2006の対比変動率から見た、各県の勝ち組・負け組み分類を私なりの基準でしてみた。
勝ち組
千葉、東京、愛知、京都、大阪、
やや勝ち組
北海道、宮城、埼玉、神奈川、静岡、滋賀、兵庫、奈良、岡山、広島、愛媛、福岡、佐賀、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、
やや負け組
山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、石川、長野、島根、高知、熊本、
負け組
青森、岩手、秋田、富山、福井、山梨、岐阜、三重、和歌山、鳥取、山口、徳島、香川、長崎、
参照

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
为翻译对汉语, 使用这
⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
⇒http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/06/17 Saturday
2006/06/17(Sat)
 6月16日から、カリブ海のセントクリストファー・ネビスで開かれている国際捕鯨委員会(IWC)の年次総会で、日本側は、初日に、無記名投票導入案を提案したが、賛成30票、反対32票、棄権1で否決された。
6月16日から、カリブ海のセントクリストファー・ネビスで開かれている国際捕鯨委員会(IWC)の年次総会で、日本側は、初日に、無記名投票導入案を提案したが、賛成30票、反対32票、棄権1で否決された。
この無記名投票導入案は、反捕鯨国や自然保護団体の圧力で捕鯨支持国が反捕鯨に回ったり、投票を棄権したりするのを防ぐのが狙いのものであった。
昨年も、日本側は、同様の提案をしたが、賛成27票、反対30票で否決されていた。
この日本側提案の投票方式の変更が可決されれば、これに続く投票で、捕鯨支持国が約30年ぶりに全体の過半数を確保できるとの予測もあっただけに、日本側としては、出鼻をくじかれた形となった。
今回の日本側の誤算は、これまで、日本側であったthe Solomon Islandsが反対に回り、 Denmarkが、棄権に回ったことにあったといわれている。
なお、Tuvalu, Palau, Kiribati, the Marshall Islandsは、日本側提案に賛成票を投じた。
参考「Solomon Islands joins anti-whaling vote」
更に、日本側と見られていたGambia と Senegalが、遅れて出席し、投票に間に合わなかったこともあった。
WWFによれば、近時のパブリックオピニオンでは、太平洋のPalau, Kiribati, Solomon Islands, Tuvalu 、Marshall Islandsの諸国のほとんどが、商業捕鯨再開に反対であるとのことである。
参照「 State urged to fight whaling 」
今年の総会時のIWC加盟国は70か国であり、捕鯨支持国が新たに3か国( Cambodia, Guatemala 、the Marshall Islands)加盟し、日本政府としては、捕鯨支持国が36、反捕鯨国が33、態度不明が1か国と、捕鯨支持国が反捕鯨国を上回っているとみていたようだ。
そして、当初の予想では、今回は、捕鯨支持派が初めて反対派を上回り、日本が総会の主導権を握るのではないかと、されていた。
しかし、たとえば、マーシャル諸島の当局者などは、「われわれは、独自路線を貫く」と、ラジオ・ニュージーランドで語るなど、これら、太平洋の中の環礁国は、日本の意のままには、ならないような情勢となっているようだ。
参照「Whale Survival at Stake in War Over Commercial Whaling」
また、たとえ、捕鯨支持国が過半数を占めたとしても、商業捕鯨再開の前提となる鯨類の新たな管理制度(RMS)の策定には加盟国の4分の3以上の賛成が必要なため、今回の総会で捕鯨再開が決まる可能性はない。
追記2006/06/19 その後のIWC総会の動向
国際捕鯨委員会(IWC)総会2日目は、日本が承認を求めた4地域の漁民によるミンククジラの沿岸捕鯨の実施が、賛成30、反対31、棄権4の小差で否決。
3日目は、1982年の商業捕鯨一時禁止決定に批判的な内容の宣言を、33対32の1票差で可決。
IWC宣言要旨
採択された宣言の要旨は以下の通り。
一、鯨類の利用は沿岸の共同体の持続的な生活、食糧安全保障、貧困の廃絶にとって重要であることを強調する。
一、国際捕鯨委員会(IWC)は、個体数の多い鯨の捕獲数を算定するための改訂監理方式(RMP)を採択、科学委員会も持続可能な捕鯨が可能であることに合意しており、商業捕鯨の一時禁止措置はもはや不要だと認識する。
一、鯨が大量の魚を消費することが、沿岸国の食糧安全保障問題となっているとの研究結果を受け入れる。
一、持続可能な商業捕鯨の再開に反対する加盟国の姿勢は(IWCの設立根拠となった)国際捕鯨取締条約の目的に反すると認識する。
一、IWCは、管理された持続可能な捕鯨を許すような保全、管理措置を取ることによってのみ、崩壊を免れると理解する。
一、文化の多様性と沿岸の人々の伝統、資源の持続可能な利用という根本的な原則、科学的に根拠のある政策と規制を尊重し、IWCの機能を正常化させることを宣言する。(
備考
太平洋環礁国の立場
IWCのメンバーではない国
Fiji, Tonga, Vanuatu, Niue, Cook Islands 、Samoa
IWCのメンバー国
Palau, Kiribati, Tuvalu 、 Nauru 、Solomon Islands、The Marshall Islands (今回からメンバー)
参照
「Japan defeated in key vote」
「Japan fails to take control of whaling commission 」
「Pacific Nations Have Opportunity To End Whaling」
「Australian whales could end up as Japanese steaks」
「Solomon Islands Reneges On Whaling Position 」
为翻译对汉语, 使用这
⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
⇒http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
Comments Off
2006/05/29 Monday
2006/05/29
 新宿・大久保の淀橋教会で、日野原重明さんのお話を聞く会があるというので、出かけてみた。
新宿・大久保の淀橋教会で、日野原重明さんのお話を聞く会があるというので、出かけてみた。
この淀橋教会、創立103年目というから、歴史のある教会のようだ。
中田重治と「東洋宣教会」の二人の宣教師とが意気投合して1901年に神田神保町に開設した中央福音伝道館を端緒とした、日本のホーリネス教会の最初の教会のようだ。
1904年に、この流れで、「柏木聖書学院」として設立されたもののようだ。
今回の日野原さんの冒頭でのお話によると、日野原さんは、この淀橋教会の第四代牧師の小原十三司さん(1942年6月26日戦争反対を唱え、官憲によって投獄されたという、ご経歴を持つようだ。ご遺言に「、“リバイバル、リバイバル”」と、いわれたという。)の最後を、医師として、看取られたということだった。
私のような仏教徒からすれば、そんなことは、ともかく、パイプオルガンの設備がいい、新装成った新教会の建設費、20億円のうち、10億円が寄付で集まったのは、すごい、などの、あらぬ下世話な方向に関心がいってしまう。
肝心の日野原さんのお話だが、「「信仰と望みと愛」の中で、一番大切なのは、愛であるが、その愛も、与えられる愛と、Tender Loveとがあって、後者は、許す、忍耐強い愛である。」とされていた。
そのためには、仕返しをしない人生が大切であるとされた。
そして、すべてを洗って、和解(Reconcile)することから、その愛は始まるとされた。
また、人間の存在とは、生きたいと願っているあらゆる生物の中に生きているのが、人間であるとされた。
更に、本当のものは、見えないものであるとも、言われた。
私は、日野原さんについては、ブログ記事「日野原重明さんの「理想の死に方」」
の中で、「日野原さんは、人生の終わりの時には、フォーレのレクイエムを聴きたいとされている。」と書いたことがあったが、今回の講演の中でも、「フォーレのレクイエムの第3楽章のあたりで、人生を終えれば、理想的だが、あまり、音楽のテンポが早くなっても、これまた、こまる。」などと、冗談を言われていた。
最後に、日野原さんは、 イギリスの詩人ロバート・ブラウニング(Robert Browning)の詩の一節「「小さな円を描いて満足するより、大きな円の、その一部分である弧になれ」(ブラウニングのサイトの25ページ「Abt Vogler」の中の「On the earth the broken arcs:in the heaven,a perfect round.」の部分を指されているのでしょうかね?
こちらのサイトもご参照)の言葉で、講演を締めくくられた。
 ところで、ここの教会には、専属の聖歌隊がいて、当日は、「What a friend we have in Jesus」、「How Great Thou Art」、「Amazing Grace」、グルックの「オルフェオとエウリディーチェ」(CW.Gluck “Orfeo ed Euridice”)のなかの 「精霊の踊り」(Dance of the blessed spirits)、「Ortonville」などを歌っていた。
ところで、ここの教会には、専属の聖歌隊がいて、当日は、「What a friend we have in Jesus」、「How Great Thou Art」、「Amazing Grace」、グルックの「オルフェオとエウリディーチェ」(CW.Gluck “Orfeo ed Euridice”)のなかの 「精霊の踊り」(Dance of the blessed spirits)、「Ortonville」などを歌っていた。
日野原さんも、この教会の聖歌隊が、日本一のカントラムになるのではないかと、賞賛されていた。
ちなみに、日野原さんは、日本音楽療法学会の会長もされている。
为翻译对汉语, 使用这
⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
⇒http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/03/12 Sunday
2006/03/12
 3月10日付けのThe Telegraph紙「NEW LOGIC FOR NEW INDIA - There was no condescension in Bush’s offer of friendship 」(Swapan Dasgupta氏の記事)は、今回のアメリカ・ブッシュ大統領のインド・パキスタン歴訪と、ブッシュ大統領とインドのシン首相との首脳会談における「原子力発電など民生用の核技術をインドに提供する」ことの合意の真意について、次のように伝えている。
3月10日付けのThe Telegraph紙「NEW LOGIC FOR NEW INDIA - There was no condescension in Bush’s offer of friendship 」(Swapan Dasgupta氏の記事)は、今回のアメリカ・ブッシュ大統領のインド・パキスタン歴訪と、ブッシュ大統領とインドのシン首相との首脳会談における「原子力発電など民生用の核技術をインドに提供する」ことの合意の真意について、次のように伝えている。
最後はスキャンダルで失脚した元大統領リチャード・ニクソン氏は、アメリカ国内での不評の時でさえ、インドにおいては、常に歓迎される立場であった。
1971年、(ニクソンは、中国とのピンポン外交の延長として、中国の国連加盟実現をサポートし、その結果)中国が、共産主義後の孤立から、ニクソンによって、救われた恩義を、中国は忘れなかった。
しかし、ブッシュ大統領が引退したのちも、今回のインド訪問におけるシン首相の首脳会談で述べられた、「原子力発電など民生用の核技術をインドに提供する」という、インド特別扱いの合意は、のちのち、ブッシュ大統領に対するインドにおける高い評価の元でのステータスを勝ちうるものとなるであろうというには、あまりにも、まだ、尚早である。
しかし、将来、歴史家が、今21世紀でのインドの外交の歴史をトレースした場合、牢固とした冷戦構造をひっくり返したという点についての唯一の功績については認めなければならないであろう。
それは、単に、この常に物議をかもし出しているブッシュ大統領が、インドに対して手を差し伸べる努力をしたということについてだけではない。
21世紀における世界秩序において、民主化インドが果たすであろう、とてつもない重要性について、理解しえた、世界最初の指導者がブッシュ大統領であった、という点についてである。
インドとアメリカの原子力エネルギーについての理解は、自然経過の過程で、起こってきたことではない。
これまで、米・印両国は、交渉しうるにいたらない、対立関係にある立場にあった。
3月2日における分離協定は、実際は、アメリカ議会の批准の手続きを経て、制度化され、国際的に容認されうるのであるが、もし、ブッシュが、インドのこの問題についての敏感性に適応させて、政治的決断をしなかったならば、この分離協定は、実現しなかったであろう。
つまり、ブッシュ大統領は、インドのために、わざわざ、核保有五カ国の主賓席に、新たに、席を設けてあげたようなものだ。
インド議会が、共産主義者とイスラム票に依存しているという、インド議会の特殊事情に助けられて、ブッシュ大統領の二日間のインド訪問のこの特殊な一面は、十分にインド国内で、宣伝されなかったばかりでなく、評価もされなかった。
もともと、今回のブッシュ大統領のインド・パキスタン歴訪については、たいして、宣伝すべき要素も、評価すべき要素もなかったはずだ。
インドのシン首相側は首相側で、インドの世界的な政治・外交上の成功を誇示する必要も、なかった。
ブッシュ大統領のほうは、アメリカ議会のほうに、歴史的なお土産を持ち帰らなければならない必要に迫られていた。
しかし、アメリカ議会だけが、このことで責められようか?
インド人民党は、7月18日と3月2日の合意につながるプロセスにおいては、インド政府が明らかにすべきいくつかの重要なポイントがあったとはいえ、過度に慎重であった。
したがって、歴史的行程を前進させることを歓迎するのは、メディアと企業の場に持ち込まれた。
インドは、まだ、新しい世界的地位に対処するには、精神的に十分用意できているとは見えない。
インドのネルーや、Nehruviansと称せられるネルーの継承者であるV.K. Krishna Menon 氏のような方は、国際的問題に対して、情熱的なまでの関心を持っていた。
不幸なことに、彼らの国際的関心事は、好戦的(CHIP ON ONE’S SHOULDER)なものであった。
ネルーは、アングロサクソン人の慣習に文化的に浸っていた人であるが、彼の熱情を持って、すべての植民地化した国民とともにいくことを示した人であった。
同様に、1950年代の外相であったMenon(Krishna MENON)氏も、宣伝者的立場から逸脱することをせず、彼は、英国におけるインド連盟のヘッドとしての役割に終始した。
世界情勢における優等生立場をとろうとする試みの中で、インドは、結局は、説教好きで、信心ぶった、退屈な国に終わるであろうと、Menon氏は、記述している。
イギリスやアメリカの要人たちは、マウントバッテン(Mountbatten)(インド総督)派や、イギリス・ロンドンのハムステッド(Hampstead)街に入り込んだリベラル派を除いては、ロンドンで買い物はするが、モスクワが天国のようなフリをする熱心なインド人よりは、1958年のパキスタンのアユーブ・カーン(Mohammad Ayub Khan)や、セイロンのコテラワラ首相(John Kotelawala)のほうが、なじみがあって気楽のような気がする。
もっとも、インディラガンジーについてみれば、彼女の凶暴なまでの国益の支持にもかかわらず、気味のわるいほどの高みへの傲慢な主張を伝えた。
屈折したスノビズムに浸ったのは、単に指導者ばかりではない。
西側世界に向けての偽装された憤慨というものは、国家的哲学であったし、結果、それは、悲惨な政策選択につながった。
インドに充満していた怠惰と、無能力は、英国植民地の遺産のせいにされた。
英知と企業家精神は、退けられ、自給自足と第三世界化を名分とした平凡さが歓迎された。
エコノミストや歴史家は、お見通しのように、悪人扱いだった。
経済学者で「 Free Trade Today」の著書でも知られている経済学者ジャグディシュ・バグワティ(Jagdish Bhagwati)教授(インドが社会主義順応をする時代に、早い時期に、避難した一人。)は、次のように言っている。
「経済学におけるいかなる初歩的ミスも、あなたが欲している推論にとっての正しい前提を素直に仮設することによって、深遠な真実に変えることが出来る。インドは、誤れる前提から予期された結果をえるという、暴政に見舞われていた。」
この問題は、市場経済学の開始や、核兵器の獲得によっても、終了しているものではない。
数年前、VSナイポール 〔Vidiadhar Surajprasad Naipaul 西インド 諸島トリニダード出身のヒンドゥー系作家)は、英国が最終的に撤退したあとの50年間の非植民地の問題に類した質問をしたところ、、「政治的公正」運動のトップから、予期せぬ敵意を直面に受けた。
この他人の気持ちを考慮しない、不快な真実は、知的仮定の再吟味をしようとするものではない。
先月、the Indian Council for Cultural Relations(これは、Nehruviansといわれるネルー信奉者たちが、著名なアーティストたちに呼びかけて後援を依頼し、母体が出来たものなのだが。)が主催して、インド文学を第三世界の経験に結びつけるセミナーを開催した。
インドの作家が西洋の市場において、インドの慣用句と経験を探しているときに、エジプトやシエラレオネ共和国での抑圧された民の声とを不自然に結び付けてしまおうとすることは、まったくの不合理性を持つものであることは、明らかである。
わかりにくい新国際情報秩序というものの持つ善というものが、前世代の遺物によってまだ宣言されているように、表向きのインドは、今世紀の、生意気で自信過剰なインドとは、十分には、折り合いをつけてくるまでにいたらなかった。
ブッシュ大統領が早くから察知していたインドのもつエネルギーと企業家的な活力は、まだ、多くの重要な意思決定の領域の中に、埋もれてしまっている。
より広い世界と、相互作用しているパラノイアの影で、新しいインドへの無理解があるのだ。
市場指向型経済や規制緩和を志向してからたった15年しか経っていないインドだが、この短い期間の間でも、インドは、恐怖に次ぐ恐怖を経験してきた。
WTOの庇護のもとで、ためらいながらも、規制された国際貿易を導入したのだが、多国籍企業によるインド経済の買収の恐れに遭遇したこともあった。
ケーブルテレビジョンが、(死人の街)アー ザムガル(Azamgarh)の不幸な村民の姿を人気テレビドラマのBaywatch に映し出し、陰険な文化帝国主義の犠牲になることへの恐れへのトリガーになった。
ほとんどあらゆる点で、これらの恐怖は、間違って置き換えられてきたということがわかる。
インドそれ自身のもつ、インド的創意や、文化的癒しは、インドをして、市場のルールを、口伝えに表していた。
そのいい例が、クリケットである。
インドに社会主義がはびこったときに、クリケットのゲームをコントロールするのは、イギリス人とオーストラリア人であった。
今日、いかなる主なクリケットの判定においても、インドの利益を分析することなくして、決定はなされえない。
70年代に、ヨークシャー生まれのフレッド・トルーマン(Trueman, Fred)が、インドのクリケットをありきたりのスポーツとして軽蔑したことがあった。
彼は、いかなるMCC(クリケット協会)の時代も、インドを旅行したことがなかった。
おなじヨークシャーの伝説的人物のGeoff Boycott氏は、インドテレビでの夕食時に歌わなければならない。
彼のアクセントは、30年前に、イギリスにおいて、忍び笑いを引き出していたピーターセラー氏のインド風振る舞いのように、古風であると、インド人には、みなされている。
この数十年での体験には、偏狭な仲間や、無知な文化的に盲目な愛国主義者たちによって、葬り去られるには、あまりに、意味のあるものを有している。
経済的に自由化されたインドが、世界に対峙するときは、いつでも、インド自身が有利になるように、勢力の均衡化が図られることで、成功してきた。
ブッシュからの友情の申し出には、これっぽっちの謙遜もないし、パキスタンと違って、彼が、兄貴づらしての finger-wagging(自ら高みに立っての『いけません』調の仕草で、人差し指を左右に降らす動作)での訓練に着手もしなかった。
ブッシュ大統領は、インドに、援助や無償供与を浴びせることもしなかった。
彼は、インドに対して、世界の資本主義での正当な役割を想定し、インド自身が豊かになることを懇願していた。
彼の申し出は、前世代の人間がもたらした刺激物の除去を容易にすることにある。
アメリカ人がするように、インド人が当然と考えている民主主義についての高尚な話のすべては、どうでもいい話なのである
ブッシュは、相互に有益な取引をするために、外では、テキサスなまりの言葉をしゃべっていた。
ネールは、憎しみに満ちた怒りを楽しむ異議申立人のように、ブッシュのロジックを理解することが出来なかっただろう。
彼は、インドの暗黒時代の典型的存在であった。
インドという国は、進んだ。
そして、若い世代は、 サルマン・ラシュディの小説、「真夜中の子供たち」とは違って、怒りをもって、浪費された50年間を振り返る必要もない。
彼らは、インドの従属的地位以外は、失うものは何もない。
彼らにとって、世界は、勝つためにあるのである。
終わり
为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/03/04 Saturday
2006/03/04(Sat)
 トリノ五輪フィギュアスケート女子で、同種目日本人史上初の金メダルを獲得した荒川静香さんの演技で゛一躍有名になった、イナバウアーだが、そのイナバウワーのスタイルを開発したのが、1941年に西ドイツで生まれたIna Bauer さん(1957年から1959年まで、ドイツのフィギア・スケーティング・チャンピオン、1958年と1959 年のWorld Championships)だというのだ。
トリノ五輪フィギュアスケート女子で、同種目日本人史上初の金メダルを獲得した荒川静香さんの演技で゛一躍有名になった、イナバウアーだが、そのイナバウワーのスタイルを開発したのが、1941年に西ドイツで生まれたIna Bauer さん(1957年から1959年まで、ドイツのフィギア・スケーティング・チャンピオン、1958年と1959 年のWorld Championships)だというのだ。
彼女のスケート技法の詳細については、このサイト『Figure skating techniques : spread eagle and ina bauer』に書かれている。
いまも、Ina Bauer Wanderpokalsという基金のようなものがあって、少女スケーターを育てる役割を果たしているようで、ご本人は、デュッセルドルフにご在住のようである。
そのIna Bauer さんの元祖イナバウアーの写真が見たくて、検索したのだが。
この写真は、1965年にペアでスケーティングするイナバウアーさん。
当時、24歳のころでしょうか。
そして、そのほかにも、21歳のときの、こんな写真や、
こんな写真
もある。
この写真は、イナ・バウァーさんが、トニー・ザイラーさんと一緒に、1960年、イナバウワーさんが19歳か20歳の時に、『Kauf Dir einen bunten Luftballon』(「虹色の風船』とでもいうのでしょうか。日本語の題名は、「白銀に踊る (1961)」でした。 )という映画に出たときの写真。
この映画の紹介では、「出演者は「ザイラーと12人の娘 白銀は招くよ!」のトニー・ザイラー、フィギュア・スケートの選手権保持者だったイナ・バウァーのほか、オスカー・ジマ、ギュンター・フィリップなど。」とありますね。
これ「Wir machen Musik」が、この映画の中の音楽。
「SCHLAGER Various Artists A-D」
参照
そういえば、この映画、オーストリアのインスブルックの店で、ビデオになって、売っていたような気がします。
規格が違いそうなので、買いませんでしたが。
いまでは、DVDになってAmazonで買えるようですね。
この後、1962年には、同じ、トニーザイラーさんとのコンビで、「EIN STERN FALLT VOM HIMMEL」(日本題名「空から星が降ってくる」)、同じ1962年に「On Thin Ice 」という映画にも出演されているようですね。
イナバウワーさんのヨーロッパチャンピオン大会での成績が、このサイトにあり、
1956, Paris, France では、13位、
1957, Vienna, Austriaでは、10位、
1959, Davos, Switzerlandでは、4位、
とのことだです。
しかし、肝心の本家のイナバウワーさんが、イナバウワーをやっている写真は、ついぞ見当たらなかったのは、残念でした。
追記 イナバウワーとは?(2006/03/04)
まゆみさんから、早速コメントをいただいたが、どうしても、荒川静香さんの演技を見ていると、上体に目が行ってしまうが、本来、イナバウワーは、この写真でみるとおり、足が、鷲が180度、羽を広げたようなかたち(これをスケート用語で、the spread eagleというらしい。)になって、スケートが、二本の平行線を描くように、横にすべることをさすらしい。
この写真やこの写真やこの写真やこの写真もご参照
上体をそらすかどうかは、二の次なんだそうで、このサイトは、昨年の3月24日の2004 Worlds in Dortmund での、いろいろなスケート選手について、Stefkaさんが一言ずつ書いたコメントだが、荒川静香のスケートについては、次のように書かれている。
「私は、荒川静香は、美しいスケーターだと、いつも思っていたのですが、彼女がこのような完璧なプログラムをこなすとは、考えたことがありません。
たった小さなミスは、彼女の最初のルッツ−3トウ・コンビネーションでのダブル・ルッツだけでした。
このミスは別にして、彼女は、絶対的に完璧で、非常なパッションを持って、スケートをし、氷上を駆け巡りました。
彼女のトゥーランドット( “Turandot” から、「誰も寝てはならぬ」(Nessun dorma)(音楽としては、このほかに、Celtic Woman-You Raise Me Upが使われていますね。歌詞は、こちら参照)の解釈も、大変に美しいものでした。
なんと、彼女のイナバウワーは、私の想像を超えたものであることでしょう。
荒川静香のイナバウワーは、”Ina Bauer”とよぶべきではなく”Shizuka “とよぶべきものであります。」
「I have always thought Shizuka Arakawa was a lovely skater but I never imagined her to skate such a perfect program: the only small mistake was doubling the lutz of her first lutz - 3 Toe combination. Apart from this, she was absolutely perfect and skated with so much passion and flow across the ice… Her interpretation of “Turandot” was breathtakingly beautiful. How she does her Ina Bauer is beyond my knowledge. You can’t call this an Ina Bauer - it’s a “Shizuka ™”.」
为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
 ブログでWordpressを使って、海外のthemesのデザインを使うと、スタイルシートが英語文字用に、設計されているために、それに日本語文字を書き込んだ場合、表示される文字が、日本語の場合は、著しく小さく表示されてしまうことがある。
ブログでWordpressを使って、海外のthemesのデザインを使うと、スタイルシートが英語文字用に、設計されているために、それに日本語文字を書き込んだ場合、表示される文字が、日本語の場合は、著しく小さく表示されてしまうことがある。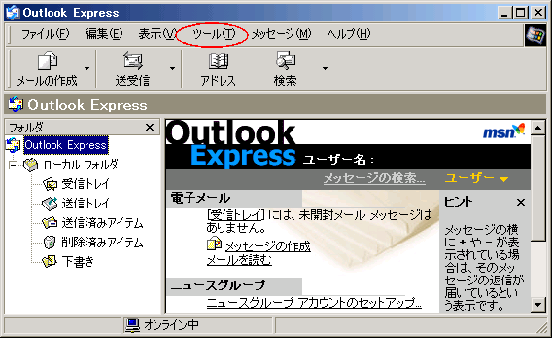 使っているメールソフトOutlook Expressで、ある日、受信ができても、送信ができなくなる場合がある。
使っているメールソフトOutlook Expressで、ある日、受信ができても、送信ができなくなる場合がある。 おそらく、皆さん方のお宅でも、家中にコンピュータが増えて、インターネットが、競合して、つながらなく場合が、よくあることだとおもいます。
おそらく、皆さん方のお宅でも、家中にコンピュータが増えて、インターネットが、競合して、つながらなく場合が、よくあることだとおもいます。 .
. .
.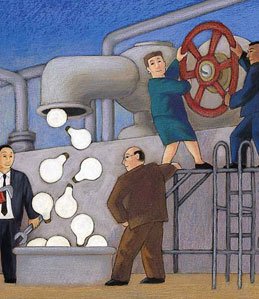 このサイト「
このサイト「 靖国神社問題に絡んで、一部に「日本にも、アメリカなどのような無名戦士の墓を」なんて声があるのですが。
靖国神社問題に絡んで、一部に「日本にも、アメリカなどのような無名戦士の墓を」なんて声があるのですが。 世界の最初の無名戦士の墓は、デンマークの「Landsoldaten」だそうで、これは、1849年に建てられたそうな。
世界の最初の無名戦士の墓は、デンマークの「Landsoldaten」だそうで、これは、1849年に建てられたそうな。 昨日、
昨日、
 6月16日から、カリブ海のセントクリストファー・ネビスで開かれている
6月16日から、カリブ海のセントクリストファー・ネビスで開かれている 新宿・大久保の
新宿・大久保の ところで、ここの教会には、専属の聖歌隊がいて、当日は、「
ところで、ここの教会には、専属の聖歌隊がいて、当日は、「 3月10日付けのThe Telegraph紙「
3月10日付けのThe Telegraph紙「 トリノ五輪フィギュアスケート女子で、同種目日本人史上初の金メダルを獲得した荒川静香さんの演技で゛一躍有名になった、イナバウアーだが、そのイナバウワーのスタイルを開発したのが、1941年に西ドイツで生まれたIna Bauer さん(1957年から1959年まで、ドイツのフィギア・スケーティング・チャンピオン、1958年と1959 年のWorld Championships)だというのだ。
トリノ五輪フィギュアスケート女子で、同種目日本人史上初の金メダルを獲得した荒川静香さんの演技で゛一躍有名になった、イナバウアーだが、そのイナバウワーのスタイルを開発したのが、1941年に西ドイツで生まれたIna Bauer さん(1957年から1959年まで、ドイツのフィギア・スケーティング・チャンピオン、1958年と1959 年のWorld Championships)だというのだ。