2005/04/13 Wednesday
2005/04/13(Wed)
 4月11日、カナダの十万人の畜産業者たちが、カナダ政府を相手取って、七十億ドルの損害賠償を求め、集団訴訟した。
4月11日、カナダの十万人の畜産業者たちが、カナダ政府を相手取って、七十億ドルの損害賠償を求め、集団訴訟した。
http://www.theglobeandmail.com/servlet
/ArticleNews/TPStory/LAC/20050411/MADCOW11/
TPNational/Canada参照
これによると、イギリスから輸入された牛の中から、一頭のBSE牛が発見されたとき、同時に輸入されていた191頭のうち、80頭についてのトレースをカナダ政府が怠ったために、それらの汚染牛のうち、少なくとも十頭が、飼料にまぎれたために、今日のカナダのBSE牛の発生を招いたものだとしている。
これらの80頭のいくらかは、食用にも紛れ込んだと見られ、また、これらが、1990年から1993年の間に、家畜の飼料に紛れ込んだものとしている。
同時にこの訴訟では、飼料の交差汚染を招いたとして、Ridley Corp. Ltd.という会社をも、訴訟の対象にあげていいる。
このRidley Corp. Ltd.社は、この会社のオーストラリアの親会社
http://www.ridleyinc.com/
では、1996年に、肉骨粉の使用を中止したにもかかわらず、このカナダのRidley Corp. Ltd.社では、大豆よりも肉骨粉のほうがコストが安いとの理由で、肉骨粉を飼料として使い続けたとしている。
一方、今日になって、今度は、カナダの畜産業者有志が、アメリカのR-CALF USAを相手取って、集団訴訟を起こそうとしていることが、わかった。
集団訴訟を起こそうとしているのは、カナダの畜産業者のJohn Morrisonさんで、Fair Market Beefという名の任意団体を作って、集団訴訟をしようとしている。
その理由として、R-CALF USAが、カナダの牛のリスクを強調して、カナダとアメリカとの生体牛貿易の再開をストップさせ、カナダの畜産業者たちに、甚大な被害を与えたというものである。
John Morrisonさんのいうに、カナダの牛は、固体認識タグをつけているために、アメリカの牛よりも、より安全であるとしている。
この集団訴訟のために、選任以上の署名を集めたいといっているが、その署名の集め方がユニークで、3月7日日付の20カナダドルの小切手に署名をするのだという。
これによって、ダブりの署名もなく、また、署名の真正性も、保たれるとしている。
とりあえずは、千人の署名を得、最終は、三万五千人の署名を集める予定だという。
集団訴訟は、来週か再来週に、先月差し止め命令を下したと同じ、モンタナ地裁に提訴するという。
7月27日に予定されているモンタナ地裁での永久国境閉鎖命令で、さらに国境再開が、R-CALFによって遅らさせられることのないように、R-CALFに対する損害賠償額は、一日あたり、7百万ドルを要求するとしている。
まさに、泥仕合と化してきたアメリカ・カナダ両国の国内事情だ。
http://www.cattlenetwork.com/content.asp?contentid=4497参照
このような中で、カナダでは、元USDAの獣医であるLester Friedlander博士が、USDAの同僚から聞いたところでは、USDAが発表しないように決めたBSEのケースがあるという証言をし、話題になっている。
博士に言ったその同僚は、リタイアが近いので、それを話すことで、年金を失うことを恐れていたので、詳細を話すことを拒絶してきたという。
しかし、彼の話によると、BSEの症状をもったテキサスの牛は、サンジェゴにあるパッキングプラントで、それをUSDAの獣医が非難した後も、レンダリングブラントへ、検査なしに送り込まれたという。
このプラントで処理された牛で、BSEの検査を受けた牛の数は、二年間に、わずか三頭であった、とのニュースがあった。
このプラントは、 Lone Star Beefというプラントで、ハイリスクのBSEにかかっていると思われる老廃牛を処理している。
Lester Friedlander博士のいうに、USDAのいうように、アメリカに、一頭のBSE牛しか発見できなかったということは、とても信用できないという。
カナダで一千二百万頭の牛から、四頭のBSEが発見されたのに、一億二千万頭いるアメリカから、一頭も発見されていないのだ。
博士の言うに、カナダとアメリカとの検査体制などは、まったく同じなので、アメリカでは、もっとBSE牛が発見されてしかるべきだという。
Lester Friedlander博士は、1995年まで、ペンシルベニアにある規模の大きいパッキングプラントで、肉の検査員を担当していた。
退職後、動物衛生に関する講演などをしている。
なお、4月12日に、以下
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/
April2005/08/c3556.html
のように、この問題について、Lester Friedlander博士のほか、Gerard Lambert 博士、Shiv Chopra博士を交えてのプレス・カンファランスが、カナダで行われるようであるし、また、Lester Friedlander博士のカナダ議会での議会証言(これは、現在カナダ議会で審議中の法案「Bill C-27, the Canadian Food Inspection Agency Enforcement Act」についてのものだ。)も、あるようだ、
このように、まさに内憂外患をかかえたUSDAなのだが、ここにきて、ジョハンズ米農務長官は、議会に対して対日経済制裁をすることへの自制を求めた。
http://www.brownfieldnetwork.com/
gestalt/go.cfm?objectid=33084540-BE7F-CD9D-DC77FEF61EF2ABB0参照
「制裁という言葉が、議会から出てきた。」として、ジョハンズ長官は、選ばれたアメリカの国会議員が、進行中の牛肉交渉について、その進歩がはかばかしくないことを理由にして、非難するという事態を憂慮した。
そして、この際、気持ちを静めて、威嚇的な行動をやめるように望んだ。
「あらゆる行動にはリアクションが伴うものであり、その結果、双方にとって、得るものは少なくなる。」といっている。
今回のカナダ畜産業者のカナダ政府への集団訴訟は、カナダとアメリカとの国境再開を一段とむづかしくさせているなかでの、弱気なアメリカのUSDAの立場を、図らずも、ジョハンズさんは、見せていることになる。
2005/04/14 追記 MASUO DOI博士が、USDA検査のズサンさぶりを証言
昨日のthe Canadian Broadcasting Corp.
http://www.cbc.ca/news/
が伝えたころによると、1997年当時、USDAの調査担当の獣医であるMasuo Doi博士は、ニューヨークのOriskany Fallsにある「と畜場」にはこびこまれた二頭の明らかに病気の牛について、検査が適宜に行われていないことを危惧し、USDAの調査部門でも、BSE検査がなされていないことを危惧していたとの発言をした。
第一のケースについては、対象の牛の脳の検査は、しなかったという。
第二のケースについては、Doi博士は、その牛がBSEでないことを示す証拠書類をえることがてきなか得ることが、できなかったという。
この報道したテレビ会社のCBC(the Canadian Broadcasting Corp.)では、数日前に、この証拠書類を手に入れたという。
しかし、この書類では、この検査にたちあったUSDA検査員の言葉として、ただ、「questionable validity−検査の妥当性に問題あり」とだけ書かれていたという。
以上が、昨日の記事だが、このMasuo Doi博士というのが、先に紹介したLester Friedlander博士が言った「元同僚」と、思われる。
http://www.ctv.ca/servlet/
ArticleNews/story/CTVNews/1113403014256_
108812214/?hub=Canada 参照
これに対して、ロイター報道によると、USDAは、この二人の証言を否定したという。
http://www.reuters.com/n
ewsArticle.jhtml?type=healthNews&storyID=8172200参照
ちなみに、このMasuo Doi博士というかたは、USDAの豚の検査を担当されていた方のようで、このサイトhttp://66.102.7.104/search?
q=cache:eaHo9rZ11C4J:www.garynull.com/
Documents/erf/mad_cow_disease_part_3.
htm+Masuo+Doi&hl=ja&client=firefox-aによると、1979年に、豚にも中枢神経が侵され、脳が、スポンジ状になるケースがあることから、「豚にもTSEがある。」との説を出されたかたのようである。
一方、このDOI博士の証言を受けて、USDAのKarl Langheindrich博士は、CBC のインタビューに対して、次のように語ったという。
http://sask.cbc.ca/regional/servlet
/View?filename=mad-cow-concerns050413参照
CBCが入手した第一回目の検査サンプルには、BSE判定の決め手となるはずの牛の脳の組織が含まれていなかったことについて、
「臨床的兆候にもとづいて、獣医によって記述がなされており、この牛の場合には、CNS(中枢神経疾患)があると、書かれている。しかし、それ以上のことを、あなた(CBC)は推定することはできない。」といったという。
http://www.obviousnews.com/breakingnews
/stories/obviousnews-556905.html
参照
2005/04/15追記 USDAは、「十分なサンプルなしにBSE検査をしたことの誤り」だけは認める
カナダのテレビ局であるCBCが「1997年に二つのBSE疑い例について、肝心の脳の組織をサンプルにせずに検査したことは、疑惑隠しだった。」と報道したことについて、USDAのRon DeHaven氏は、BSEと診断するに足りうるに十分なサンプルなしに、検査したことについては、誤りを認めたが、それらの牛は、BSEではなかったことを強調した。
http://calgary.cbc.ca/regional/servlet/
View?filename=ca-mad-cow-usda20050414
参照
Ron DeHaven氏によると、「われわれにとっては、とりうる二つの選択肢があった。ひとつは、手持ちのサンプルで、検査をすることであり、もうひとつの選択肢は、まったく検査をしないという選択肢であった。
もし、われわれが、BSE隠しをしようとするのであれば、検査をまったくしないということについて、議論していたであろう。この場合、われわれは、前者の「手持ちのサンプルで検査をする」という選択肢をとった。そのサンプルの不十分さを補うために、われわれは、三つの異なる方法での検査を行ったのである。」といった。
2005/05/06追記 OIGがフリードランダー博士から事情聴取
カナダ議会で、アメリカのBSE検査隠蔽疑惑事件を証言したもとUSDA検査官のフリードランダー博士だが、このほど、OIG(Office of Inspector General)http://www.usda.gov/oig/の Keith Arnold氏やWilliam Busby氏から事情聴取を受けたようだ。
OIGに調査を命じたのは、USDAのPhyllis Fong氏であるとされる。
今後の展開が注目される。
なお、これをUPI通信(United Press International )が執拗に追っている。
下手をすれば、ビーフ・ゲート事件に進展する気配すらある。
参考記事はいずれもUPIの記事で、固有名詞が、これまでの登場人物である Lester Friedlande、Masuo Doi などに加えて、Pat McCaskey氏や、Karl Langheinrich氏や、Joe Oziano氏など、ごろごろ出てきた。
参考記事
「Feds probing alleged mad cow cover-up」
http://www.upi.com/view.cfm?StoryID=
20050429-020831-9428r「No sign of mad cow in 1997 cows」
http://www.upi.com/view.cfm?StoryID=
20050415-124715-6918r「Experts: First 1997 mad cow false alarm」
http://www.upi.com/view.cfm?StoryID=
20050415-025007-7820r「Experts: No mad cow in second 1997 animal」
http://www.upi.com/view.cfm?StoryID=
20050415-032421-7972r
 Translate
Translate
HOME-オピニオン-提言-情報解説-発言-プロフィール-図書館-掲示板262
2005/04/13(Wed)
 どうも、日本人の性格として、国際基準などとなると、律儀に守らなければならないような感じにとらわれるのだが、OIE基準をめぐる輸出国・輸入国の思惑は、もっと娑婆臭いものようだ。
どうも、日本人の性格として、国際基準などとなると、律儀に守らなければならないような感じにとらわれるのだが、OIE基準をめぐる輸出国・輸入国の思惑は、もっと娑婆臭いものようだ。
で、OIE基準、輸入国安全基準、輸出国安全基準、SPS協定、この四者の相互関係を見てみると、次のようになるのだろう。
まづ、安全に対する厳しさの度合い順にならべてみると
輸入国安全基準 > 輸出国安全基準 > OIE基準
という順番は、大方はなるだろう。
となれば、輸入国の思惑としては、安全基準が、実質、隠された貿易障壁として機能するためには、OIE基準ができるだけ厳しくなって、「輸出国安全基準の底上げをはかる効果」を持たせたほうが好ましい。
輸出国の思惑としては、OIE基準ができるだけ緩やかになって、「隠された貿易障壁が低くなり、輸出マーケット拡大に資する効果」を持たせたほうが好ましい。
そこで、SPS協定の登場なのだが、
「輸入国安全基準 マイナス OIE基準」の安全度の差の評価について、輸入国・輸出国の思惑として、
「危険性の評価を行うに当たり、入手可能な科学的証拠」が輸出国から提出されていない場合には、「第五条 7」にもとずいて「暫定的に衛生植物検疫措置を採用」と、輸入国は、WTOの場で、主張することができるが、
「危険性の評価を行うに当たり、入手可能な科学的証拠」があると、輸出国が主張している場合には、「第二条 2」にもとずいて「衛生植物検疫措置を、(中略) 十分な科学的証拠なしに維持しないことを確保する。」ことに違反していると、輸出国は、WTOの場で、主張することができる。
つまりは、 OIE基準をより低い安全水準にしたほうが、「輸入国安全基準 マイナス OIE基準」の安全度の差の評価についての「科学的証拠」が立証不可能の差にまで拡大させることになり、輸出国は、「第二条 2」にもとずいた「イチャモン」を、輸入国に対してつけやすいというわけだ。
こうなると、ほとんどの農産品を輸入に依存しなければならない日本としては、国際安全基準をめぐっては、つねに、牛肉と同じような立場に立たされていることになりますね。
たとえば、すでにパネル紛争になっているアメリカ輸入リンゴの火傷病問題をめぐる紛争
http://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-j050.html#_Toc483278843
がいい例ですね。
アメリカ牛肉問題の帰結は、日本の食料自給率の向上こそ、根本の解決策となるようです。
 Translate
Translate
HOME-オピニオン-提言-情報解説-発言-プロフィール-図書館-掲示板261
2005/04/05 Tuesday
2005/04/05(Tue)
 先に述べた北米三国(カナダ・メキシコ・アメリカ)の統一BSE対策の詳細がわかりました。
先に述べた北米三国(カナダ・メキシコ・アメリカ)の統一BSE対策の詳細がわかりました。
詳細はサイトhttp://www.usembassycanada.gov/content/can_usa/madcow_bseharmonization.pdfにあり、全文仮訳は次のとおりです。
.
「BSE戦略の統一化に関する、北米首席獣医担当官(CVO)による報告書」(Report of the North American Chief Veterinary Officers on Harmonization of a BSE Strategy)
.
.
要約
メキシコ・カナダ・アメリカの動物の健康に関する上級担当官は、2005年3月17日に、メキシコで、北米のBSEリスクの効率的な管理方策のための共通最小基準の確立についての討論の結果をまとめた。
この結論は、しかるべき公衆衛生担当者たちを含むこれまでの会合において、結論に達したものである。
これらの会合は、三国地域内において、血液ならびに血液由来製品の貿易についての正常化をゴールにめざして、また、BSEに関するOIE基準と一致した国際的BSE戦略の促進を、CVO(the Chief Veterinary Officers)が、科学的根拠にもとづいたフレームワークを創出しようとして、開催されたものである。
メキシコ・カナダ・アメリカ三国において、等しいBSE対策を確立し導入することで、公衆と動物の健康を護り、安全な貿易の回復が出来るであろう。
.
最小基準
これらの会合の結果として、CVOは、北米におけるBSE方策の一連の最小基準を作り出した。
これらの最小基準は、メキシコ・カナダ・アメリカの各国における、しかるべき動物の健康と公衆衛生の担当者に対し、示されるであろうし、それゆえに、まえもって、決定しておかなければならないものであるべきである。
この文書は、現在貿易されている製品については、必要条件とは、ならないものである。
危険部位
輸出目的の牛肉については、次のものは、食用ルートに入ることを許されない、危険部位となる。
月齢30ヶ月以上の牛の脳、頭蓋、眼、三叉神経節、脊髄、脊柱、そして、後根神経節。
月齢にかかわらず、扁桃、回腸遠位部(distal ileum)。
危険部位除去の方法は、交差汚染が最小になるような方法でなされなければならない。
歩行困難牛
歩行困難牛を「と蓄」したものは輸出禁止
現在、メキシコとカナダは、歩行困難牛をアメリカへの輸出用工場への「と畜」に向けることを禁止する政策を実行中である。
アメリカとしては、「と蓄場」に現れた、すべての歩行困難牛と、障害牛を、廃棄する政策を採る。
CVO(Chief Veterinary Officers)としては、ダウナー牛を「と蓄」から排除するのは、BSEとは、関係のない理由にもとづくものであるとの立場をとる。
カナダは、現在、福祉的観点から、障害を持つ牛を輸送することを禁じる規則をつくっている。
加えて、彼らには、代替的な方策が、BSEに対する等しい防護策として、用意されるであろう。
たとえば、子牛のように、非常に若齢の牛であって、BSE感染物質に感染してのものとはみなされないものについての代替方策である。
同じように、老齢の牛で、明らかな理由で障害を持っている牛-たとえば、「と蓄場」への輸送の途中で傷ついたような場合には、獣医は、BSEの症状とは一致しないものとの決定を下すことが出来る。
最後になるが、歩行困難牛であって、BSE検査が陰性になった場合には、EUや日本では、その肉を食用ルートに入れることは、排除されていない。
スタンニング
ピッシング(スタンニングの後、細長い竿状のものを頭蓋の空洞にさして、中枢神経を傷つけること)と空気注入スタンニングは、禁止される。
機械的肉分離過程
危険部位除去を前提として、適当なプロセスが管理されるべきである。
たとえば、月齢30ヶ月以上の牛について、頭蓋や脊柱から、機械的に肉を採ることは、禁止される。
輸入管理
ミルク、精液、胎児などの特定製品については、輸出国のBSEリスク如何にかかわらず、安全に貿易確保がなされなければならないが、一定の製品については、BSE汚染国からの貿易は、制限される。
その他の製品については、輸出地域の相対的なリスクと、輸入を意図する製品の相対的なリスクとにもとづいて、輸入措置がなされなければならない。
サーベイランス
CVOは、ハイリスクの牛に焦点をあわせたサーベイランスこそ、BSEがもし存在するとしたら、それが、もっとも効率的な方法であるということを、重ねて言いたい。
能動的に、的を得たサーベイランス・プログラムは、その対象地域における成牛の総数に焦点を当てて検出するために、実施される。
現在のサーベイランス・プログラムは、現在実施されているサーベイランス・プログラムの結果とあわせて、2005年5月のOIE総会において、全面的な調整がなされるであろう。
血液由来飼料の制限
血漿タンパクを排除することをも含む、BSE感染物質の拡大と流布を防ぐための、効果的な飼料規制の達成と、交差汚染の回避と、検査行動の実施
個体認識システム
適切に牛の個体認識がなされることが、サーベイランス・サンプリング・システムの完全性を確実なものとさせるし、疫学上のトレースバック(とくに、牛の出生集団へのトレースや、リスク物質への曝露の継続的ポイントへのトレース)を確実なものとさせる。
北米地域においての個体認識システムの各国間の互換性については、各国のシステムが整備されるにつれ、考慮していかなければならない。
リスク・アセスメント
4つの部分にもとずいて、国や地域の牛の総数のリスク・ステータスの決定。
4つの部門とは、リリース・アセスメント、曝露アセスメント、因果関係アセスメント、リスク評価 の4つである。
北米三国との貿易
北米三国内で、最小基準が実施されることで、地域内の生産物が、安全に貿易されることを、CVOは、考えている。
長期のゴールとしては、血液および血液由来製品の貿易が、OIE基準の条件に一致していく一方で、最小基準が実施されるまでの短期間の間に、域内貿易は確立されなければならないと、CVOとしては、認識している。
牛肉と、副生物
公衆衛生・動物の健康の保護を前提としての、危険部位を除いた、骨付き・骨なしの牛肉、食用・非食用副生物の、月齢にかかわらない、貿易。
危険部位の除去は、BSE疑惑牛に対する防御を条件として、公衆衛生を護り、効果的な血液由来飼料規制を可能とするための、効果的方策である。
生体牛
北米三国内での最低基準は、域内生体牛の貿易についても、適用する。
この際、生体牛の個体認識によるトレーサビリティと、維持は、この場合のキーファクターである。
とくに、危険部位除去と、飼料規制について、直ちに「と蓄」される生体牛か、肥育牛かにかかわらず、域内生体牛取引を可能とする保護措置としての、最小基準の設定が必要である。
その他の血液や、肉骨粉を除く血液由来製品の移動
その他の血液や、肉骨粉を除く血液由来製品の移動については、BSEの観点からの制限は、なされないであろう。
この場合は, 他のTSE管理プログラムでの生血条件が適用されるであろう。
らくだ類・鹿類の移動について
らくだ類(アルパカなど)・鹿類や、それらを原料とする製品の移動については、BSEの観点からは、制限しない。
月齢にかかわらず、牛からの扁桃、回腸遠位部、そして、それらを含むいかなる商品も、食品、飼料、肥料、化粧品、生物学的または医学的装置を含む医薬品としては、貿易してはならない。
さらに、「と蓄」時期の月齢が、30ヶ月または、それ以上の牛については、その牛の脳、頭蓋、眼、脊髄、脊柱、そして、それらから由来した蛋白製品は、食品、飼料、肥料、化粧品、生物学的または医学的装置を含む医薬品としては、貿易してはならない。
注1 血液と血液由来製品とは、「と蓄」に先立って、圧縮空気やガスを頭蓋の空間に注入する方法でのスタンニング・プロセス、または、ピッシングプロセスによらない血液と血液由来製品である。
注2 これらの最小基準の貿易への適格性については、2005年5月に開かれるOIE総会で、さらに検討されるであろう。
獣関係生物製剤
これらについては、牛の危険部位由来のものでないこと、個々のリスクアセスメントに従うものであること。
ペットフード
OIE基準では、ペットフードに関する規定がないので、輸入国のリスクアセスメントに従うものとする。
非牛由来のペットフードについては、輸出国においての獣医の保証があれば、安全に貿易できる。
非蛋白の牛脂と、この牛脂からの派生物
不溶性不純物質が重量比最大0.15パーセント以下のレベルのものであれば、輸入に制限はない。
この移動や輸入に際しては、この基準を満たす牛脂であることの証明書類を必要とする。
合意文書署名者
メキシコ
SAGARPA-SENACIAのディレクタージェネラル
アメリカ
USDA・APHISのアドミニストレイター
カナダ
CFIAのチーフ獣医オフィサー
以上
 Translate
Translate
HOME-オピニオン-提言-情報解説-発言-プロフィール-図書館-掲示板 (more…)
2005/04/03 Sunday
2005/04/03
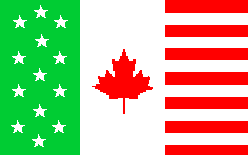 「米国、カナダ、メキシコは1日、食肉からの脳や眼球など特定危険部位の除去や、感染源となり得る肉骨粉飼料の禁止など、9項目の最低基準を満たせば域内の牛肉貿易を認めることを柱とする3カ国統一の牛海綿状脳症(BSE)対策を策定したと発表し、これをOIEの改正会議で国際統一ルールとするように働きかけるとのことである。
「米国、カナダ、メキシコは1日、食肉からの脳や眼球など特定危険部位の除去や、感染源となり得る肉骨粉飼料の禁止など、9項目の最低基準を満たせば域内の牛肉貿易を認めることを柱とする3カ国統一の牛海綿状脳症(BSE)対策を策定したと発表し、これをOIEの改正会議で国際統一ルールとするように働きかけるとのことである。
この「カナダ・メキシコ・アメリカの統一BSE対策」(Canada, Mexico And United States Release Harmonized North American BSE Strategy)の概要は、USDAのサイトhttp://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p
/_s.7_0_A/7_0_1RD?printable=true&contentidonly=
true&contentid=2005/04/0113.xmlで、次のように発表されている。
以下、概訳である。
「カナダ・メキシコ・アメリカの三カ国は、一致した北米BSE戦略を発表した。
科学的根拠をベースにしたBSEのためのリスクマネージメント方策の枠組みが、北アメリカ内での反芻動物ならびに反芻動物製品の正常化した貿易の助けになることを目的として、開発された。
そして、これは、OIEガイドラインに沿った国際的なBSE戦略となることをも、目的としている。
この戦略は、また、OIEを通じて、国際的な一致を持ったBSEリスク緩和策を促進するための、更なる討論の一部として、OIEへ提出されるであろう。
このレポートの中で定義されているミニマム基準は、北アメリカ内では、これまで、成文化は、されてこなかった。
むしろ、これらは、それぞれの国において、個々の国での規定のプロセスを通じて、動物の健康担当局や公衆衛生担当局で、考えられるべきものであろう。
これらの勧告は、現在貿易されている製品についての要件変更実施を求めるものではない。」
以上が、その内容である。
また、この合意に先立って、アメリカとカナダとの反芻動物の貿易に関する規則について、いくつかの改訂が行われ、この改訂は、NAFTA間のOIE基準に準拠した輸入緩和措置の前触れをなす内容と憶測される。
すなわちその内容とは、次のとおりである。
http://canadagazette.gc.ca/partII/2005/20050331-x2/
html/extra2-e.html参照
1.この「反芻動物とそれらの製品の輸入禁止に関する規則」は、規則が発効する2005年6月30日以前には、適用しない。
2.生体動物については、精液採取用の雄の鹿、雄の牛、雄のラム、の輸入を可能とする。
3.月齢30ヶ月以下の肥育用牛についても、輸入を可能とする。ヤギや羊については、月齢12ヶ月以下のものであって肥育用のものや、直ちにと畜去れるものについては、輸入を可能とする。
4.肉製品については、骨なしの羊肉・ヤギ肉については、輸入を可能とする。また、月齢12ヶ月以下の動物の臓物については、輸入を可能とする。
5.化学肥料の成分や、 動物性食品の禁止範囲は拡大され、それらの中に反芻動物由来の物質が含まれている場合には、輸入禁止とされる。
以上である。
これらの戦略の下敷きになっているのは、2004年4月27日に、Julie A. Caswell氏とDavid Sparling氏の両氏によって書かれた「RISK MANAGEMENT IN THE INTEGRATED NAFTA MARKET:LESSONS FROM THE CASE OF BSE」という論文である。
http://www.farmfoundation.org/naamic/cancun/caswell.pdf参照
この論文は、カナダ・メキシコ・アメリカのNAFTA加盟三国共通の「牛肉インテグレーション」を実現するための課題について、詳細に分析しているもので、たとえば、難航している日本との牛肉貿易再開のための戦略として、次のように記載している。
日本との貿易再開のためには、二つの観点からのアプローチが必要であり、一つは、OIE基準遵守をふリかざしてのもの、もう一つは、アドホック(場当たり的)な戦略としての短期的なもので、その内容として、次のように書かれている。
「日本との牛肉貿易再開が難航している、その間に、カナダ・メキシコ・アメリカのNAFTA 加盟三国は、アドホックをベースにした国境再開のためのステップをすすめなければならない。
三国共通のインテグレートされた生体牛と牛肉の市場構築のために重要なことは、NAFTA 非加盟国との貿易について、影響を与えることである。それらNAFTA 非加盟国との牛肉貿易再開にあたっては、リスクマネージメントシステムのインテグレーションを、それ自体の中に含まれなければならない。」
図らずも、日本との牛肉貿易再開問題で、あらわになったかのように見える北米三国(カナダ・メキシコ・アメリカ)の生体牛・牛肉製造業のNAFTA加盟国間でのインテグレーション構想だが、この構想は、もともと、NAFTA発足時から、あったものだ。
サイトhttp://www.card.
iastate.edu/iowa_ag_review/summer_03/article4.aspx
は、アメリカでのBSE発生前のものであるので、若干適切性を欠くが、NAFTA加盟国での生体牛・牛肉貿易戦略をよくあらわしているので、あらためて掲載しておく。
この中のチャート図
http://www.card.
iastate.edu/iowa_ag_review/summer_03/images/4-1.gif
が、その現状をよくあらわしている。
2002年の時点での数字だが、ここでは、次のようになっている。
カナダは、アメリカに百五十四万頭の生体牛と、五百七十六万頭の豚を輸出していた。
これらのアメリカが輸入していた生体牛の31パーセントが肥育牛であり、68パーセントが肥育豚であるとした場合、これらの牛や豚は、アメリカ国産の牛や豚用に加えて、追加七百三十九万ブッシェルの穀物コーンと、二十七万八千万トンの大豆ミールを飼料として消費していたことになる。
これらの牛・豚が米国内でと畜されたとした場合、牛の畜量は、牛で4.3パーセント、豚で5.7パーセント増えていたことになる。
また、カナダの家畜は、牛肉で三十八万九千百六十七トン、豚肉を三十八万三千八百七十六トンを、2002年の時点で、アメリカへ輸出していた。
同時に、アメリカは、八十二万八千六百六十八トンの牛肉と、五十四万九千九百八十九トンの豚肉を、輸出していた。
これらが累積して、カナダのと蓄される生体牛と肉の輸入量は、アメリカの牛肉輸出量の55パーセント相当、豚肉輸出量の100パーセント相当になっていた。
これに、肥育用の牛や豚の分もカウントすると、アメリカの牛肉や豚肉の輸出量に貢献する度合いは、もっと高くなってきていた。
一方、カナダからアメリカへの輸出は、生体牛十二万七千頭、豚九千二百五十二頭、牛肉八万三千八百二十六トン、豚肉六万四千三百三十八トン、と、微々たるものであった。
この、片務的ともいえるカナダ・アメリカ間の生体牛・牛肉の貿易関係は、と蓄規模の点でも、飼料コストの低廉度の点からも、消費者の肉消費量の点からも、カナダ側に対して、アメリカ側が、圧倒的に、勝っていたことから、必然的に生まれたものだ。
このような状況の構図を変えて、たとえば、カナダのアメリカへの輸入を減らすことになれば、カナダの肉の輸出は必然、これまでのアメリカから輸出されていた国へのカナダからの輸出へと向かうであろうから、アメリカの生産が拡大しないかぎり、アメリカの肉輸出量は、それだけ、減少することになる。
メキシコの牛肉生産体制は、衛生面や政治社会状況が影響していて、北米赤肉複合体(the North American red meat complex )の結成までにはいたっていないが、肉の輸出入量は、確実に伸びている。
とくに、脂肪のない肉 (muscle meat)の生産が特徴で、これへの需要が伸びているようである。
メキシコは、アメリカに対して、生体牛八十万頭、牛肉六千三十二トンを輸出している。
一方メキシコは、アメリカに対して、生体牛十万六千頭、豚十六万九千頭、牛肉二十七万一千六百七十一トン、豚肉十五万七千四百二トンを輸出している。
カナダとメキシコとの関係は、ほとんどない。
以上が、2002年時点でのカナダ・メキシコ・アメリカ間の牛肉などの貿易関係であるが、今回の北米三国(カナダ・メキシコ・アメリカ)の統一BSE戦略の意図は、図らずも、これまでBSE問題のカナダ・アメリカ両国の発生で中断していたこれら構想の復活条件を整える狙いがあるものと思われる。
参照 http://pods.dasnr
.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-1997/F-580web.pdf
しかし、このNAFTA三国での生体牛・牛肉インテグレーション構想に対しては、アメリカ国内でも反対がある。
たとえば、カナダ国境再開に対して反対の立場をとっているR-CALFの最高執行者Bill Bullard氏は、このインテグレーション構想について、次のように言っている。
http://pryordailytimes.
com/articles/2005/03/25/
news_content/community_news/agriculture/agriculture02.txt
参照
「カナダから牛肉製品を輸入しやすくするために、輸入標準規格を下げるという、多国籍ミートパッカー構想によって、日本や韓国のようなアメリカ牛肉主要輸出先顧客に対して、その牛肉貿易を再開させようとするUSDAの考えかたは、非論理的で、理性のないものである。
2003年以来、日本は、われわれに、こういってきた。「アメリカの牛肉が、カナダから来たものでないことが保証されないうちは、そして、その牛肉に、アメリカ産のものであると適切に示されていない限り、われわれは、アメリカの牛肉をほしいとはおもわない。」と。
どうして、アメリカの巨大ミートパッカーたちは、原産国表示制度(COOL制度)の実施をしたがらないのか?
もし、アメリカ政府が、海外の巨大市場の要求を無視することをやめるならば、アメリカの巨大パッカーも、中小パッカーも、原産国表示ラベルがあろうと、BSE検査があろうと、等しく、ビジネスの発展を見るであろう。
アメリカの牛肉の他の顧客の要求を前向きに満たすことが、それらの国々との良好な関係改善につながりうるのだ。」
一方、施行が延びに延びているアメリカの原産国表示制度(COOL)の実施が、この構想に不利な状況を与えるのではないかと、とくに、カナダでは、懸念する声が強いようだ。
http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200301/145785050.pdf参照
 Translate
Translate
HOME-オピニオン-提言-情報解説-発言-プロフィール-図書館-掲示板254
2005/03/31 Thursday
2005/03/31(Thu) 13:24
 アメリカ通商代表部は、今日発表された「National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE)」に関する報告書の(題名は、「The National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers」)の中で、日本の牛肉貿易障壁について記述している。
アメリカ通商代表部は、今日発表された「National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE)」に関する報告書の(題名は、「The National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers」)の中で、日本の牛肉貿易障壁について記述している。
ここで、日本との牛肉貿易再開は、top priorityの問題であり、今後とも、それに向けて、あらゆるレベルでのプレッシャーを日本に与えていくとしている。
また、日本側とは、extensive documentationを用意して協議を続けているが、このextensive documentationには、対日経済制裁は、含まれていない、としている。
以下にその内容を詳述し、紹介する。
316ページ
牛肉保護措置について
アメリカは、同様の考えを持つパーティとともに、日本でBSEが発生したことによって日本が課した、日本の牛肉保護措置について、反対を表明してきた。
日本の牛肉保護措置は、ウルグァイラウンドの間での取り決めにおいて、日本への輸入の急増によって、日本国内生産者が重大なダメージをうける場合には、保護措置をとることが出来ると、取り決められていた。
その保護措置は、輸入の増加率が、前年の財政会計年度の四半期累積分において、前年度に比して、17パーセント増になった場合に、始動するものとなっている。
いったん、始動した保護措置は、当該会計年度の残余期間まで、残存する。
始動した場合、チルドビーフに課する関税は、38.5パーセントから50パーセントに、増加する。
2002年と2003年においては、日本でのBSE発生によって、日本が非定型的な市況にあることを考慮してくれとの、もっとも高度のレベルでの日本政府からの懇願によって、アメリカは、日本政府に対して、牛肉国内保護措置の適用を認めた。
この保護措置は、アメリカでのBSE発生による日本のアメリカ牛肉禁輸措置の結果、2004年4月に、解除された。
アメリカは、ドーハ開発アジェンダ(2001年11月、第4回WTO閣僚会議で採択された、新ラウンド立ち上げの閣僚宣言)での牛肉保護措置の変更を取りきめるよう意図している。
317ページ
農産物関税引き下げについて(訳は、省略)
320ページ
牛肉
日本の牛肉市場のアメリカへの開放については、2004年における総務貿易に関する、ブッシュ政権の最優先事項であった。
日本は、2003年のアメリカでのBSE発生以後、アメリカ牛肉についての禁輸措置を課してきた。
中略
2004年4月に、技術的会合が、もたれて以来、アメリカは、日本政府に対して、ひろい範囲にわたった、ハイレベルの、日本市場再開のための努力をすることを、日本政府に対して、誓ってきた。
アメリカの政府関係者たちは、何度となく、日本に飛び、また、日本関係者たちのアメリカへの訪問を計画してきた。
それは、フィードロットへの視察や、研究室、そして、牛肉処理加工プラントへの視察にまで及んだ。
ブッシュ大統領と小泉首相とは、この問題に付いて、何度となく、話し合った。
牛肉貿易が再開しうる条件を取り決める交渉が、何度となく、延期された後、1昨年10月25日に、日米両国は、牛肉貿易再開のためのフレームワークについて、合意を見た。
この合意は、日米両国の牛肉貿易再開に道を開くことが出来るように意図されたものであった。
さらに、この合意においては、牛のグレーディングー格付け−と月齢との相関関係についての追加研究までの暫時の特別マーケティングプログラムのもとに、貿易が再開できるようにしたものであった。
6ヶ月間の部分的な牛肉市場開放運用の後に、このプログラムは、日米牛肉貿易が、より正常化された形で成されうるように、再検討されるべきものであった。
アメリカは、アメリカ牛肉についての科学的疑問点や、消費者安全に付いての疑問点などについての、日本側のあらゆる疑問点の払拭に取り組んできた。
われわれは、この牛肉貿易再会という最重要な問題に付いて、牛肉貿易が再開されるまで、アメリカ政府のあらゆるレベルで、強く求め続けていくつもりである。
原文は、以下のサイト
http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications
/2005/2005_NTE_Report/asset_upload_file427_7478.pdf参照
ご参考
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=
10000101&sid=afQZWjmer5MM&refer=japan
http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific_
business/view/140113/1/.html
http://www.ustr.gov/Document_Library/Reports_Publications/
2005/2005_NTE_Report/Section_Index.html
 Translate
Translate
HOME-オピニオン-提言-情報解説-発言-プロフィール-図書館-掲示板253
2005/03/26 Saturday
2005/03/26(Sat)
 R-CALFの最高執行者Bill Bullard氏が、声明を出したが、その中で、現在の日米の牛肉問題について、次のようにいっている。
R-CALFの最高執行者Bill Bullard氏が、声明を出したが、その中で、現在の日米の牛肉問題について、次のようにいっている。
以下概訳開始
アメリカの牛肉産業にとって不幸なのは、カナダからの生体牛の輸入によって、BSEフリーのアメリカを、BSEリスクのあるアメリカへと、わが身を置き換えてしまったことだ。
The National Meat Association (NMA) は、3月2日に下されたカナダ国境再開差し止め裁判所命令を覆そうとしているが、この行動自体、アメリカの消費者の安全よりも、利益を重んじている行動であることを表している。
日本や韓国がアメリカの牛肉を再び買ってもらう一番いい方法は、そして、カナダと、再び、しっかりした貿易関係を築くために一番いい方法は、USDAが、消費者と牛肉産業を守ることをはじめることであり、そのためには、ブッシュ政権の対外貿易政策に対して、右顧左眄しないことである。
USDAの構想としてあげられている「多国籍パッカー構想」(the multi-national packers)は、カナダからの牛肉製品の安全基準を低める構想であり、日本や韓国に対して牛肉製品貿易の門戸を開かせられることを意図した構想のようであるが、この構想自体は、非論理的で、理性のない構想である。
2003年以来、日本は、われわれに、こういってきた。「アメリカの牛肉が、カナダから来たものでないことが保証されないうちは、そして、その牛肉に、アメリカ産のものであると適切に示されていない限り、われわれは、アメリカの牛肉をほしいとはおもわない。」と。
どうして、アメリカの巨大ミートパッカーたちは、原産国表示制度(COOL制度)の実施をしたがらないのか?
もし、アメリカ政府が、海外の巨大市場の要求を無視することをやめるならば、アメリカの巨大パッカーも、中小パッカーも、原産国表示ラベルがあろうと、BSE検査があろうと、等しく、ビジネスの発展を見るであろう。
アメリカの牛肉の他の顧客の要求を前向きに満たすことが、それらの国々との良好な関係改善につながりうるのだ。
以上 概訳終わり。
http://pryordailytimes.com/articles/
2005/03/25/news_content/community_news/agriculture/agriculture02.txt
 Translate
Translate
-HOME-オピニオン-提言-情報・解説-発言-プロフィール-図書館-掲示板-249
2005/03/25 Friday
2005/03/25(Fri)
どういう意図かわからないが、昨日から、「OIEが、牛肉の輸出入規制を大幅に緩和する新たな国際基準の原案を日本に提示した」とのニュースが、声高に流れている。
もともと、OIEの「Terrestrial Animal Health Code」は、毎年見直しているのであり、また、昨年10月25日の米国産牛肉の日米高級事務レベル会合合意においても、「5.BEVプログラム概説」において、「再検討されるべき情報には、次のものが含まれる。」として「再検討すべきOIE基準にもとづいた、アメリカのBSEの状態」との一行がはいっているのである。
問題のポイントは、OIE基準が緩和されるかどうかということよりも、SPS協定との関係を考慮しなければならないのに、マスコミ報道では、そのことについては、一切触れていないのか、どうしたものなのであろうか?
すなわち、前にも書いたように、日本の場合のように、OIE基準よりも厳しい基準で、BSE汚染国からの牛肉輸入を禁止する場合は、SPS協定の5条2項での「(輸入する牛肉についての)危険性の評価を行うに当たり、入手可能な科学的証拠」が、不十分な状況の元での、5条7項の「暫定的に衛生植物検疫措置を採用」により、禁輸措置を行っているのであり、それに対して、第2条第2項「2 加盟国は、衛生植物検疫措置を、(中略)第五条7に規定する場合を除くほか、十分な科学的証拠なしに維持しないことを確保する。」の条項を盾にとって、「十分な科学的証拠があるのに、衛生植物検疫措置をとっているのは、隠れたる貿易障壁である。」と主張しているところに、対立点があるというわけである。
なお、今回のOIE基準の緩和要求のポイントは、は、 OIEの「Terrestrial Animal Health Code」のArticle 2.3.13.14. Article 2.3.13.15. Article 2.3.13.16. Article 2.3.13.17.Article 2.3.13.19. Article 2.3.13.21.に関するものであって、
第一に、BSEフリーの国または、最小(minimal)のBSE汚染国から輸入される骨付き、または、骨を除去した肉、または、肉製品については、輸出国において、検査が必要であるということ、
第二に、BSEリスクが中位または 高位にある国からの牛肉や肉製品については、すべての牛の検査が必要だということ、
第三に、食用や、飼料や、 肥料や、化粧品や医薬品向けに使用される牛脂について、、最小(minimal)のBSE汚染国または、また、BSEリスクが中位の国からの牛からのものについては、Article 2.3.13.19. 規定の組織を使っていないかどうかの検査が必要であるということ、
この点についての基準緩和要求と見られる。
今日の島村宜伸農水相は、閣議後会見で、OIEが基準緩和案を提示したことについて、脊髄反射的に「日本としては当然反対していく」と述べた
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050325-00000114-jij-pol
というのだが、
いやみを言うわけではないのだが、これは、上記にも書いた昨年10月25日の米国産牛肉の日米高級事務レベル会合合意において、「5.BEVプログラム概説」において、「再検討されるべき情報には、次のものが含まれる。」として「再検討すべきOIE基準にもとづいた、アメリカのBSEの状態」について合意したものと矛盾する発言ではないかと、アメリカに言われるのではなかろうか。
(日米合意の中で”The United States BSE status according to OIE criteria to be reviewed”と書いてある。)
むしろ、日本の農林水産省として、今、見解を統一しておくべきは、WTO提訴の場合にそなえた、SPS協定との関係である。
この場合に一番参考になるのが、アメリカとEUとの、ホルモン牛肉紛争における、SPS協定の解釈だ。
http://lin.lin.go.jp/alic/week/1998/jan/323eu.htm
問題となったSPS協定抵触部分は、三箇所あった。
1 危険性の評価(SPS協定第5条1項)
2 恣意的かつ不正な保護水準の適用(SPS協定第5条5項)
3 保護の水準(SPS協定第3条)
これを今の日米間の牛肉問題に置き換えてみると、アメリカ側の言い分は、次のようになるだろう。
1.「日本側が提示した科学的報告は輸入禁止の根拠にならないので、SPS協定第5条1項違反なのではないのか?」
2.「日本側は、検疫衛生措置の保護水準を、、恣意的かつ不正に区別し、貿易に差別や偽装した制限をもたらしているので、SPS協定第5条5項違反なのではないのか?」
3.「日本側の輸入禁止措置は、OIE基準の月齢30ヶ月未満を、月齢20ヶ月未満の牛に引き上げるなど、OIEの国際基準に基づいておらず、また、独自の水準を採用できる規定にも該当していないので、第3条1項違反ではないのか?」
ということになるのだろうか?
したがって、アメリカ側からWTO提訴があった場合の対策としては、この上記三点の逆を考えればいいことになる。
最後に、OIE基準に過大な期待をいだかれがちな方がたのために、次のUSDAのQ&Aの日本語訳をしておく。。
律儀な日本人は、「国際基準履行」などと迫られると、悪いことをしているなどと思って、おびえがちであるが、このようなあけすけなものを読むと、ショック療法としては、いいのかもしれない。
http://www.beef.org/uDocs/BSE%20Final%20QA%2011-17-2003.pdf参照
「OIE基準は、履行のハードルが高い規則でも、履行のスピードが急がれる規則でもありません。
OIEは、加盟国の主権を尊重し、動物に関する貿易について、それぞれの国の尺度にあった基準が作れるような、ガイドラインとなっています。
現在のOIE基準でのリスク地域の分類は、5分類あって、それは、BSEフリーの国、一時的にBSEフリーの国、最小のBSEリスクを持つ国、中位のBSEリスクを持つ国、高位のBSEリスクを持つ国、に分かれています。
それぞれのカテゴリーにある国についての牛肉貿易について、OIEガイドラインは、適用されます。
どの国から、牛肉や牛肉製品を輸入できるかのOIE基準は、至極簡単で、次の二つの条件のうちの一つが該当しさえすればいいのです。
その条件の一つとは、その国が、BSEを持たない国であること、その条件のもう一つは、その国が BSE発生のケースがあった場合には、適切な飼料禁止措置がなされていて、そのような飼料禁止措置後、少なくとも、7年間は、BSE発生事例がなかったこと、です。
OIEのガイドラインは、これらの条件を、必ずしも、牛肉貿易の必須条件にはしていないのです。
OIEでは、BSEフリーの条件を決めてはいますが、国際社会においては、これらの条件が、牛肉貿易をする決定要素とはなっていないのです。
実際、いかなるリスクカテゴリーにある国との貿易についても、たとえ、その国が、ハイリスクのBSEリスクカテゴリーにある国であっても、OIEは、アドバイスしているのです。
ここで重要なことは、一定のBSEリスクがある諸国間では、消費者の信頼性にかかわらず、牛肉は、生産され安全に消費されているということです。」
2005/03/28追記
骨なし牛肉にかかわるOIE基準部分
OIEが、本年5月の総会において提出を予定しているとされる「骨なしの牛肉について、輸出国のBSEリスクにかかわらず、どのような条件も要求すべきでない」との部分は、現行のOIE基準である「Terrestrial Animal Health Code (2004)」では、次の条項で、次のように定められている。
5月総会で提案されるであろうOIE基準の変更は、下記条項についてのものと見られる。
Article 2.3.13.13.
「一時的にBSEフリーの国や地域から、輸入する場合には、その国の生体牛からの骨付きまたは骨なしの生牛肉や牛肉製品については、獣医管理局は、検査済みであることを国際的に証明する証明書の提示を必要とする。」
Article 2.3.13.14.
「最小のBSEリスクのある国や地域から、輸入する場合には、その国の生体牛からの骨付きまたは骨なしの生牛肉や牛肉製品については、獣医管理局は、検査済みであることを国際的に証明する証明書の提示を必要とする。」
Article 2.3.13.15.
「中位のBSEリスクのある国や地域から、輸入する場合には、その国の生体牛からの骨付きまたは骨なしの生牛肉や牛肉製品については、獣医管理局は、検査済みであることを国際的に証明する証明書の提示を必要とする。」
Article 2.3.13.16.
「BSEのハイリスクにある国や地方からの輸入の場合には、獣医管理局は、生体牛からの肉や肉製品については、以下のことについて、検査済みであることを国際的に証明する証明書の提示が要求される。」
その「以下のこと」とは、
「3.輸出される生肉であって、もし、それが、月齢9ヶ月以上の動物から採った肉である場合は、骨が取り除かれ、骨を除去する過程において、神経リンパ節を含まず、それらすべてが、組織との交差汚染を回避しうるやり方で、完全に取り除かれたもの。」
「4. 輸出される肉製品であって、それが、骨除去肉からのものであり、Article 2.3.13.18.のポイント1とポイント2にリストアップされた組織を含まないものであり、かつ、牛のづ骸骨や脊柱から、機械的に除去分離された肉でないものであり、去れらのすべてが、それらの組織と交差汚染を回避しうる方法で取り除かれたもの」
参考
Article 2.3.13.18.のポイント1
「中位の、またはハイリスクのBSEリスクのある国から輸入した、いかなる月齢の牛からの、次の商品ならびにそれら商品によって汚染された商品については、食品、飼料、肥料、化粧品、生物製剤を含む調合薬、医療用具、扁桃腺、腸、それらから抽出したたんぱく質製品の調製品として、貿易してはならない。
それらの商品を使った食品、飼料、肥料、化粧品、生物製剤を含む調合薬、医療用具を、商取引してはならない」
Article 2.3.13.18.のポイント2
「中位の、またはハイリスクのBSEリスクのある国から輸入した、と畜時の月齢が12ヶ月以上である、生体牛からのものについて、次の商品や、それらによって汚染されたいかなる商品について、食品、飼料、肥料、化粧品、生物製剤を含む調合薬、医療用具、扁桃腺、腸、それらから抽出したたんぱく質製品の調製品として、貿易してはならない。
それらの商品を使った食品、飼料、肥料、化粧品、生物製剤を含む調合薬、医療用具を、商取引してはならない。」
 Translate
Translate
-HOME-オピニオン-提言-情報・解説-発言-プロフィール-図書館-掲示板- 246
2005/03/19 Saturday
2005/03/19(Sat)
 来日中のライス米国務長官(US Secretary of State Condoleezza Rice)が、今日、上智大学で行う予定のアジア政策に関する演説の事前原稿が公開され、この中で、アメリカ牛肉の輸入再開問題について、「この問題については科学的根拠に基づく国際基準が存在する。国際基準に基づいて解決を図るべき時だ。」と訴えている。
来日中のライス米国務長官(US Secretary of State Condoleezza Rice)が、今日、上智大学で行う予定のアジア政策に関する演説の事前原稿が公開され、この中で、アメリカ牛肉の輸入再開問題について、「この問題については科学的根拠に基づく国際基準が存在する。国際基準に基づいて解決を図るべき時だ。」と訴えている。
おそらく、そのいわれる『科学的根拠にもとづく国際基準」とは、「ミニマル・リスク論」であり、「ミニマル・リスク地域」を指すのであろう。( OIEの「Terrestrial Animal Health Code (2004)」の「Article 2.3.13.5.」
日本語で見られたいかたは、次のサイトhttp://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/eisei/bse/iinkai/siryo1-2.pdfをご参照。ただし、これは、2001年のコードである。
2004年のコード改定についての論点は、http://www.oie.int/eng/Session2005/A_RF2004_WP.pdfをご参照)
これがOIEガイドラインに沿ったものとして認知されることによって、SPS協定もクリアでき、WTOの場でも、パネル設置が出来る環境に、本来は至ったはずだったのだが。
しかし、その『科学的根拠に基づく国際基準』をはじめて適用しようとしたカナダが、アメリカ議会自らの手で、否定されてしまっているではないのか?
その矛盾にどうこたえられるのですか?
ライスさん。
かつて、日本の池田勇人さんが、ドゴール大統領に「トランジスターの商人」(ドゴール大統領が池田総理と会われた後、側近に『今会ったトランジスタ・セールスマンの名前、なんていうんだっけ?( “Who is that transistor salesman?”)』と、聞いたというのだが、本当かどうかは、よくわからない。)と言われたそうだが、、まさか、ライスさん、「牛肉の商人」( “Who is that beef salesman?”)なんては、いわれたくはないでしょう。
そうですねえ。
上智大学で、ライスさんにプラカードを掲げるとしたら、ボードに書く一番有効なメッセージは、「アメリカは、日本の消費者の口を、汚染されたカナダ牛肉のゴミ捨て場にするな!!」(The United States must not make a Japanese consumer’s mouth the garbage of the polluted Canada beef.)「アメリカは、カナダとの国境を開放してから、日本に圧力をかけるべし!!」ってとこですかね。
もちろん、そんなことはしないでくださいよ。
やはり、今のアメリカにとっては、カナダ牛肉のことを言われるのが、一番つらいのではないのでしょうかね。
そこが、最大の矛盾でしょうからね。
しかし、日本のマスコミは、この点についての追求は一切しないというのも、よく教育されたというか、よく飼いならされたもんですね。
そのマスコミですが、今日の産経新聞で、「日本政府が、食品安全委員会に対して、諮問する事項を、牛の感染価から人の感染価に絞って諮問する』という記事が出ていますが、この記事の意味するところが、ちょっとわかりかねますね。
記事によれば、「政府が、食品安全委員会への諮問項目を絞る方針を決め」「輸入される米国牛肉の食肉の安全性に絞ったリスク評価を求め」「米国の牛の感染リスクよりも、実際に人が食べる食肉の安全性に絞って、人への感染リスクを評価することを重視」して、諮問項目を絞るというのですが。
一見すっきりしているようで、重大な抜け穴がありますね。
牛肉にまつわるリスクには、三つあって、「プリオン感染への牛のリスク」、「vCJD感染への人のリスク」そして、「プリオン感染した牛からvCJD感染する人への、種の壁を越えた感染リスク」とがあるわけですね。
この産経新聞さんの言われる「絞った諮問項目」ですと、諮問項目を、この三つのリスクのどれに絞るというんですかね。
USDAがこよなく愛される例のハーバード大学のリスクアナリシス(the Harvard-Tuskegee Risk Model Study)(Evaluation of the Potential for Bovine Spongiform Encephalopathy in the United States)ですと、牛への感染価と、人への感染価とをごちゃまぜにして考えているのだが、これに対して、SSCでは、これらの二つの感染価(cattle oral ID50と、human oral ID50)は、セパレートして考えるべきだとしていますね。
参考 1.ライスさんのいわれる「科学に基づいた国際的な基準」としてのOIE基準について
OIEの「健康基準」( Health standards)の中には、「陸生動物の健康基準」(Terrestrial Animal Health Code)というのがあって、その中は、「パート1」の「一般条項」(General provisions)と、「パート2」の「特異的疾患についての勧告」(Recommendations applicable to specific diseases)と、「パート3」の「付録」(Appendices)と、「パート4」の「国際的証明事例」(Model international veterinary certificates)とに分かれていて、BSEについての勧告は、そのうちの「パート2」の「特異的疾患についての勧告」(Recommendations applicable to specific diseases)のなかの、「セクション2.3.脳疾患」(SECTION 2.3. BOVINE DISEASES)の中に書かれている。
この「セクション2.3.」は、さらに、15のチャプターに分かれており、BSEについては、このうちの「チャプター2.3.13 BSE」( CHAPTER 2.3.13. Bovine spongiform encephalopathy)
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_2.3.13.htm
に書かれている。
さらに、このチャプターは、22の項目(Article 2.3.13.1.からArticle 2.3.13.22.まで)に分かれていて、その中での「BSEフリーの国やゾーン」(BSE free country or zone)の定義としては、「Article 2.3.13.3.」に、「地域的にBSEフリーの国やゾーン」(BSE provisionally free country or zone)の定義としては、「Article 2.3.13.4.」に、「最小のBSEリスクのある国やゾーン」(Country or zone with a minimal BSE risk)の定義としては、「Article 2.3.13.5.」に、「中庸のBSEリスクのある国やゾーン」(Country or zone with a moderate BSE risk)の定義としては、「Article 2.3.13.6.」に、「BSEハイリスクの国やゾーン」(Country or zone with a high BSE risk)の定義としては、「Article 2.3.13.7.」に書かれているというわけだ。
そこで、アメリカは、このうちの「Article 2.3.13.5.」に、カナダやアメリカを当てはめようとして、ファイナルルールというものを作ったというわけだ。
http://nowherethoughts.net/sarpysam/archives/2005/03/05.html参照
この「Article 2.3.13.5.」には、さまざまな条件があるが、カナダに当てはめた場合、このうち、もっとも問題なのは、『飼料規制の有効性』という項目なのだ。
アメリカのように、今のOIEのArticle 2.3.13.5.活用で、「暫定正常国」扱いになりたい国というものは、現在は、BSEフリーであっても、将来のことを考えて、OIEのArticle 2.3.13.5.活用を主張してきている国も含めて、徐々に増えてきているように感じている。
現在、BSE に関する OIE Chapter の適用を国際的に改善するよう要求しているグループとして、the Five Nations Beef Group(アメリカ、オーストラリア、カナダ、メキシコ、ニュージーランド)といわれるものがあるが、これらの国々は、BSE に関する OIE chapter に関連した国際的現状の改善要求をしている。
また、OIE加盟国の多くが現行のOIE ガイドラインに従わずに牛肉輸入を禁止している現状を踏まえ、本グループはchapter のより科学的な改正を進めているOIEの対応を支持するとしている。
これらの国々は、the Five-Nations Beef Conference (FNBC) という会合を持っている。
このグループが、オーストラリア、ニュージーランドを皮切りにして、今度は、いわゆるケアンズグループ( アルゼンチン、オーストラリア、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、パラグアイ、南アフリカ共和国、タイ、ウルグアイ 16カ国)をまき込もうという状況のようだ。
http://www.abc.net.au/rural/tas/stories/s1037025.htm
http://www.meatnz.co.nz/wdbctx/corporate/docs/FILE011093.HTM
参照
一方、SPS協定(衛生植物検疫措置の適用に関する協定 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)には、
「第三条 措置の調和」に
「3 加盟国は、科学的に正当な理由がある場合又は当該加盟国が第五条の1から8までの関連規定に従い自国の衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を決定した場合には、関連する国際的な基準、指針又は勧告に基づく措置によって達成される水準よりも高い衛生植物検疫上の保護の水準をもたらす衛生植物検疫措置を導入し又は維持することができる(注)。」とあつて、その(注)として「注)この3の規定の適用上、「科学的に正当な理由がある場合」には、入手可能な科学的情報のこの協定の関連規定に適合する検討及び評価に基づいて、関連する国際的な基準、指針又は勧告が自国の衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を達成するために十分ではないと決定した場合を含む。」とあり、
また、
「第五条 危険性の評価及び衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))の決定」のなかの
「6 第三条2の規定が適用される場合を除くほか、加盟国は、衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を達成するため衛生植物検疫措置を定め又は維持する場合には、技術的及び経済的実行可能性を考慮し、当該衛生植物検疫措置が当該衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を達成するために必要である以上に貿易制限的でないことを確保する。(注)」の(注)として「(注)この6の規定の適用上、一の措置は、技術的及び経済的実行可能性を考慮して合理的に利用可能な他の措置であって、衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を達成し、かつ、貿易制限の程度が当該一の措置よりも相当に小さいものがある場合を除くほか、必要である以上に貿易制限的でない。」とあり、
また、
「7 加盟国は、関連する科学的証拠が不十分な場合には、関連国際機関から得られる情報及び他の加盟国が適用している衛生植物検疫措置から得られる情報を含む入手可能な適切な情報に基づき、暫定的に衛生植物検疫措置を採用することができる。そのような状況において、加盟国は、一層客観的な危険性の評価のために必要な追加の情報を得るよう努めるものとし、また、適当な期間内に当該衛生植物検疫措置を再検討する。」とある。
現在の日本とアメリカとの牛肉貿易途絶の状況は、日本側が、SPS協定五条2項での「(アメリカの牛肉についての)危険性の評価を行うに当たり、入手可能な科学的証拠」が、不十分な状況の元での、五条7項の「暫定的に衛生植物検疫措置を採用」により、アメリカからの牛肉がストップしている状態にあると主張しているのに対して、
アメリカ側は、OIEの「Article 2.3.13.5.」を根拠にして、昨年12月29日に、「Final Rule」を策定し、この「Final Rule」が、SPS協定三条3項の「科学的に正当な理由がある場合」に該当するとし、また、五条の「危険性の評価」をした上で、五条6項の「衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を達成するため衛生植物検疫措置を定め又は維持する場合」に該当するとしている。
また、アメリカについては、「緩和されたリスク」(“risks are mitigated”)についての概念が、日米の隔たりとなっている。
参考2.OIEの「Terrestrial Animal Health Code (2004)」の「Article 2.3.13.5.」
第2.3.13.5条
B S E 低発生国または地域
以下の条件を満たす場合は、BSEの低発生国または地域であるとみなされる。
1) 第2.3.13.1条に記載された基準を満たし、国内または地域内に存在する24ヶ月齢以上の牛に関して、過去12ヶ月間について計算された国産の牛におけるBSE発生率が、100万分の1例以上ないし100万分の100例以下である。
または、
2) 第2.3.13.1条に記載された基準を満たし、上記1) の条件で計算されたBSE発生率が、連続した12ヶ月を1単位として4単位(48ヶ月)の間、100万分の1例を下回っている。
かつ、
3) 感染牛ならびに、
a) これらの牛が雌の場合は、発病の前後2年以内にその牛から生まれた最後の子牛、
b) 感染牛と同一牛群の中で感染牛が生まれた12ヶ月以内に生まれた牛、または生後1年間感染牛と一緒に飼育された全ての牛であって、いずれの場合も、生後1年間感染牛が摂取した飼料と同様の汚染した可能性のある飼料を摂取している可能性がある牛が国内または地域内で生存していた場合は、と殺され完全に処理されていること。
24ヶ月齢以上の牛に関して過去12ヶ月間について計算した国産牛におけるBSE発生率が100万分の1例以下であるが、第2.3.13.1条1)に述べられたリスク分析の結果、BSE暫定清浄国または地域の基準の少なくとも1つを満たしていない国または地域は、BSEの低発生国または地域とみなされるものとする。
Article 2.3.13.5.
Country or zone with a minimal BSE risk
The cattle population of a country or zone may be considered as presenting a minimal BSE risk should the country or zone comply with the following requirements:
1.
a risk assessment, as described in point 1 of Article 2.3.13.2., has been conducted and it has been demonstrated that appropriate measures have been taken for the relevant period of time to manage any risk identified;
2.
a level of surveillance and monitoring which complies with the requirements of Appendix 3.8.4. is in place, and:
EITHER
1.
the last indigenous case of BSE was reported more than 7 years ago, the criteria in points 2 to 5 of Article 2.3.13.2. are complied with and the ban on feeding ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants is effectively enforced, but:
1.
the criteria in points 2 to 5 of Article 2.3.13.2. have not been complied with for 7 years; or
2.
the ban on feeding ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants has not been effectively enforced for 8 years;
OR
2.
the last indigenous case of BSE has been reported less than 7 years ago, and the BSE incidence rate, calculated on the basis of indigenous cases, has been less than two cases per million during each of the last four consecutive 12-month periods within the cattle population over 24 months of age in the country or zone (Note: For countries with a population of less than one million adult cattle, the maximum allowed incidence should be expressed in cattle-years.), and:
1.
the ban on feeding ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants has been effectively enforced for at least 8 years;
2.
the criteria in points 2 to 5 of Article 2.3.13.2. have been complied with for at least 7 years;
3.
the affected cattle as well as:
*
if these are females, all their progeny born within 2 years prior to and after clinical onset of the disease, if alive in the country or zone, are permanently identified, and their movements controlled, and when slaughtered or at death, are completely destroyed, and
*
all cattle which, during their first year of life, were reared with the affected cattle during their first year of life, and, which investigation showed consumed the same potentially contaminated feed during that period, if alive in the country or zone, are permanently identified, and their movements controlled, and when slaughtered or at death, are completely destroyed, or
*
if the results of the investigation are inconclusive, all cattle born in the same herd as, and within 12 months of the birth of, the affected cattle, if alive in the country or zone, are permanently identified, and their movements controlled, and when slaughtered or at death, are completely destroyed.
参考
「Canada: a minimal BSE risk country」
http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/
bseesb/minrise.shtml
「Comments on Proposed Rule - Docket No. 03-080-1 - “Bovine Spongiform Encephalopathy: Minimal Risk Regions and Importation of Commodities”」
http://www.inspection.gc.ca/english/
anima/heasan/disemala/bseesb/americ/comment/commente.shtml
「Comments by Japan on the propos ed amendment on the BSE Code in December 23,2003」
http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/eisei/bse/oie_e.pdf
「What risks need to be managed or mitigated?」
http://www.e-government.govt.nz/docs/workspace-2/chapter10.html
http://216.239.63.104/search?q=cache:TK_aqyP80G8J:mkaccdb.cec.eu.int/
cgi-bin/spsview/barrierintSPS.pl%3Fbnumber%3D970208++
OIE+criteria++review%E3%80%8CTerrestrial+Animal+Health+Code&hl=ja&client=firefox-a
参照
2005/03/20追記
アメリカ国務省から、ライス長官の昨日の上智大学での講演内容が発表されています。
下記のサイトです。
質疑応答についても記載されています。
その他の来日中の日本の報道各社とのインタビューの内容などは、このサイト
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/
にリンクされています。
上智大学講演での、牛肉に関する部分は、次の箇所です。
「われわれの太平洋地域における繁栄は、経済活動に最善を期することに対しての信頼と漸進的理解の賜物であります。
しかし、時々、この太平洋地域間では、貿易紛争も起こります。
もちろん、最近の日本のアメリカ牛肉輸入問題についても、そうであります。
いまや、この問題を解決するときがまいりました。
私は、日本の皆様に、次のことを保障したいと思います。
すなわち、アメリカの牛肉は、安全であるということ、そして、私ども、アメリカ人は、世界の人々に対しても、また、アメリカの人々に対しても、そして、日本の人々に対しても、食の安全性というものに対して、深く念頭においているということです。
それらを包括しうる科学的な世界標準というものがあるのであり、私どもは、より大きな繁栄を享受する手段である、投資や貿易が出来るような環境を危機にさらすような、例外的状況をそのままにしておくわけにはいかないのです。」
Our Pacific prosperity relies on trust and a growing understanding of economic best practices. From time to time, however, trade disputes do arise among us. The latest, of course, is about Japanese imports of American beef products.
The time has come to solve this problem. I want to assure you: American beef is safe, and we care deeply about the safety of food for the people of the world, for the American people, for the Japanese people. There is a global standard on the science that is involved here, and we must not let exceptionalism put at risk our ability to invest and trade our way to even greater shared prosperity.
牛肉問題に付いてのライス国務長官の昨日の記者会見での見解
アメリカ国務省サイトにおける牛肉貿易再開問題に付いて発表されたライス国務長官の記者会見での模様である。
「最近の牛肉製品貿易における混乱については、私も、アメリカ政府も、アメリカ議会も、アメリカ国民も、気にかけている問題です。
アメリカの牛肉は安全です。
われわれは、アメリカの食料安全保障や食品の安全について、そして貿易相手国の食料安全保障や食品の安全については、非常に気を使っています。
そして、私は、町村外務大臣に対して、この問題に付いては、科学的根拠にもとづいた国際標準があることを前提にして、これらの問題が解決出来るように、もしくは、出来るだけ迅速に、解決するように努力を傾けていただけるように頼んだところです。」
In that regard, I did note my concern, and the concern of the American administration and the American Congress and people about the recent disruption in our trade in beef products.
American beef is safe. We care greatly about food security and safety in the United States, and about the food security and safety of our trading partners. And I urged the minister to resolve, or to put in place, efforts to resolve these issues as quickly as possible, given that there is indeed a science-based standard that is global on this issue.
質疑応答
「そして、私は、長い時間がかかってきた、次の点について、町村大臣に対して、指摘させていただきました。
実際、これは、科学的に根拠のある国際標準がある問題であり、われわれとしては、日本が科学的な根拠にたった標準にしたがっていただきたいということ、そして、食の安全が、アメリカの牛肉にとって非常に重要な問題であるということであるということについてであります。
そして、牛肉輸入再開という問題が、日本とアメリカならびにアメリカ政府との関係において、非常に重要な問題であるゆえに、私は、牛肉輸入の早期再開を日本にのぞむものであります。」
And I made the following point to the Minister that this has gone on for a very long time. That in fact, there is a science-based standard internationally, and we would hope that Japan would follow that science-based standard, and that food safety is extremely important to the United States. American beef is safe. And we hope for an early resumption of the beef imports because this is a very, very important concern of the United States and the United States government.
全体の原文については、以下のアメリカ国務省サイトをご参照
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/43653.htm
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/43655.htm
 Translate
Translate
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_2.3.13.htm
为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
 Translate
Translate
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2005/03/13 Sunday
2005/03/13(Sun)
 米国は3月9日に開かれた世界貿易機関(WTO)動植物検疫措置(SPS)協定に関する会合で、日本に米国産牛肉の輸入再開を正式に求めたというのだが。
米国は3月9日に開かれた世界貿易機関(WTO)動植物検疫措置(SPS)協定に関する会合で、日本に米国産牛肉の輸入再開を正式に求めたというのだが。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050313-00000688-jij-int
例のアメリカ下院議会での対日経済措置の決議の中でも、こう書かれていた。
「WTOにおけるSPS合意は、WTOのメンバーに対して、SPS施策を、科学的根拠にもとづいて、人間や動物や植物ブラントの健康保護のためにのみ、適用することを求めている。
中略
SPS合意は、WTOの加盟国に対して、勝手に、貿易差別や貿易制限をする権利を許すとは規定していない。」
として、あたかも、日本がSPS協定(衛生植物検疫措置の適用に関する協定;Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)を政治的に利用しているがごとき表現があった。
しかし、どちらが、SPS協定を政治的に利用しようとしているのであろうか。
SPS協定(全文は、次のサイトhttp://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm 日本語では次のサイト http://organization.at.infoseek.co.jp/wto/sps-/sps-j0.htm)は、WTO加盟国が人、動物または植物の生命、健康を保護する措置について、貿易に対する悪影響を最小限にするための国際的規律を定めたもので、これには、
1.国際的な基準がある場合(SPS協定3.1条遵守)
2.国際的な基準がない場合(SPS協定2条 、5条 遵守)
とがあり、
さらに、国際的な基準がある場合には、
1.国際的基準よりも高い、または、異なる保護を求める場合(SPS協定3.3条)
2.国際的基準と同等の保護を求める場合(SPS協定3.1条)
とがあり、
さらに、
「国際的基準に基づかない措置が例外的に認められる場合」(SPS協定3.3条規定。SPS協定5条遵守を条件)として、
1.科学的に正当な理由がある場合
2.自国の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を決定した場合(SPS協定5.1から5.8条の関連規定遵守)
とがあり、
「国際的な基準がある場合」(SPS協定5条)
1.危険性評価(risk assessment)をする場合
2.危険性管理(risk management)をする場合
とがある。
「国際的な基準がない場合」(SPS協定5条)にも
1.危険性評価をする場合
2.危険性管理をする場合
とがある。
現在の日本のアメリカの牛肉に対する状況がどの段階にあるかといえば、
「第五条 危険性の評価及び衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))の決定」
において、
「1 加盟国は、関連国際機関が作成した危険性の評価の方法を考慮しつつ、自国の衛生植物検疫措置を人、動物又は植物の生命又は健康生育に対する危険性の評価であってそれぞれの状況において適切なものに基づいてとることを確保する。」のなかでの
アメリカがBSE発生という「状況」において
「適切なものにもとづいて」「危険性の評価」をしようとしているのだが、、
「2 加盟国は、危険性の評価を行うに当たり、入手可能な科学的証拠、関連する生産工程及び生産方法、関連する検査、試料採取及び試験の方法、特定の病気又は有害動植物の発生、有害動植物又は病気の無発生地域の存在、関連する生態学上及び環境上の状況並びに検疫その他の処置を考慮する。」の中における
「(アメリカの牛肉についての)危険性の評価を行うに当たり、入手可能な科学的証拠」が、不十分な状況の元において、
「7 加盟国は、関連する科学的証拠が不十分な場合には、関連国際機関から得られる情報及び他の加盟国が適用している衛生植物検疫措置から得られる情報を含む入手可能な適切な情報に基づき、暫定的に衛生植物検疫措置を採用することができる。そのような状況において、加盟国は、一層客観的な危険性の評価のために必要な追加の情報を得るよう努めるものとし、また、適当な期間内に当該衛生植物検疫措置を再検討する。」のなかの、
「科学的証拠が不十分な場合には、関連国際機関から得られる情報及び他の加盟国が適用している衛生植物検疫措置から得られる情報を含む入手可能な適切な情報に基づき、暫定的に衛生植物検疫措置を採用することができる。」の規定にもとづいて、
「暫定的に衛生植物検疫措置を採用」し、アメリカからの牛肉の輸入をストップしている状態にあるのであり、なんら、SPS 協定に、背馳しているものではない。
それに対して、アメリカ側が言いたいのは、第2条第2項「2 加盟国は、衛生植物検疫措置を、(中略)第五条7に規定する場合を除くほか、十分な科学的証拠なしに維持しないことを確保する。」の条項を盾にとって、「十分な科学的証拠があるのに、衛生植物検疫措置をとっているのは、隠れたる貿易障壁である。」と主張しているところに、対立点があるというわけである。
なお、SPS 協定の実施根拠としてコーデックス(国際食 品規格委員会)とOIE(国際獣疫事務局)による基準に従うかどうかについては、国際間で、異論がある。
以上のように、このSPS 協定というのは、どちらかといえば、予防原則としてみなされるために、貿易相手国との関係において、これが、見えざる貿易障壁になっているとの指弾を受けがちなものである。
また、それぞれの国の裁量政策にゆだねられている点に、その限界を指摘する声もある。
欧州委員会は、アメリカからのホルモン牛肉をSPS協定のもつ予防原則を理由に、排除しているし、アメリカはアメリカで、南米からの牛肉を、口てい疫を理由に排除している。
つまりは、アメリカが、日本の牛肉貿易についてSPS 協定遵守をしていないと言い出せば、それは、お互い様ということになるのだが。
おまけに、このSPS 協定には、「同等性の原則」と言うのがある。
「同等性の原則」とは、輸出国の基準が輸入国と異なっていても、輸出国の基準が適切なものであると客観的に証明できれば、輸入国は輸出国の基準も自国と同等のものとして扱うという原則である。
すなわち、表面的には、なんら拘束力のないコーデックス(国際食 品規格委員会)やOIE(国際獣疫事務局)に、緩やかな基準を出させ、これをもとに、SPS 協定を振りかざして、SPS 協定加盟国に遵守を迫れば、極端に言えば、どのようなことも可能なわけである。
もし輸出国の基準が適切なものであるとされれば、輸入国は自国の基準を満たしていないことを理由にその食品の輸入を拒否することはできない。
OIEを巻き込んで、SPS 協定加盟国に、輸出国優先のゆるい基準を遵守させようとしているのは、むしろアメリカのほうなのではなかろうか?
なお、アメリカは、今回「ファイナル・ルール」を作成し、カナダを、「BSE Minimal Risk」の地域とすることについて、2003年11月4日付けで、WTO規定にもとづいて、「WTO Notification G/SPS/N/USA/828」の文書でもって、「Docket No: 03-080-1 Title: Bovine Spongiform Encephalopathy; Minimal Risk Regions and Importation of Commodities Contact Person」との題をもって、対象国に対して、コメントを求めた。
http://economics.ag.utk.edu/market/LiveCattleRule10-31-03.pdf参照
このコメント期間中に、アメリカでは、2003年12月23日に、BSEが発生したのであるが、継続し、コメント期間は、2004年4月7日をもって終了した。
日本は、くしくも、アメリカでのBSE発生直後の、2003年12月26日に、在米日本大使館のTadashi SATO氏から、USDAに対し、以下の文書
https://web01.aphis.usda.gov/BSEcom.nsf/
0/a544c311876be1df85256e08005271ee?OpenDocument&AutoFramed
が提出された。
この文書において、日本側は、「Docket No. 03-080-1」についての回答として、要約、次のような内容のものを出している。
「このたび、USDAから提案された修正提案に対して、アメリカがBSE発生国でないという前提で、以下のコメントをするということを確認するものである。
日本側としては、また、2003年12月23日BSE発生とのUSDA発表後のBSEについての近時または将来を考慮した追加コメントをする権利を留保しておきたい。
同時に、日本政府としては、もし、状況が許せるのであれば、コメント締め切り期間の延長を求めたい。
日本政府は、アメリカが提案した枠組みを、反芻動物ならびに反芻動物由来のものの、それらの領域への輸入について、不必要な輸入禁止措置を取り除き、同時に、現在のBSE対策にともめられていると同等の水準の防護措置を維持できることを意図しているのであると理解している。
日本としては、提案された方策が健全で普遍化沙汰科学的原理をベースにして、差別のない方法で適用されるという前提で、それらの基本的な目的をサポートするものである。
(中略)
このような意味において、アメリカは、OIE基準(OIE Code)に定められているような世界的な基準やSPS協定と一致した防護基準でもって、アメリカ国内基準を作られることを望むものである。
もし、輸入国側が、コ内的な事情などを考慮して、アメリカ側が設定した基準よりも、高い基準を設定した場合には、二国間の問題に矮小化することは、望ましくない。
これら、二つの基準が共存しうるような解決策が、この際求められると考える。
今回のアメリカの最終規則は、OIE基準に比して、いくつかの点で、あいまいなところがある。
その結果、提案された修正事項は、アメリカが、「Minimal Risk 地域」の範囲をあいまいな方法で、ひいてしまう権限を有してしまうことになりかねない。
もう一つの問題は、アメリカの提案する「Minimal Risk 地域」が、OIE基準でいうところの「中位のBSEリスクにある地域や国」を含んでしまう危険性がある。
さらに、危険部位についても、OIE基準よりも後退しており、単に、腸の除去だけで、「Minimal Risk 地域」からの輸入が要求されているだけであることも問題である。」
以上が、2003年に日本側が、アメリカに提出した、コメントの概要である。
これらの日本側のコメントを、今の時点で見ると、「カナダを初のthe minimal-risk regionとして、認める。」と受け取れる表現があるなど、すでに、この時点で、アメリカに言質を与えてしまったような記述が、随所に見られる。
その中でも、決定的なのは、次の表現であろう。
「日本政府は、アメリカのおかれたポジションというものを、よく理解しています。なぜなら、日本とアメリカのような巨大貿易国にとって、すべての貿易国に対して、必要な場合に、遅滞なく、同時に、そして、適切に、再類別することは、不可能であるからです。そのことからして、再類別については、それぞれの国での個々の要求にもとづいてはじめることは、不可避なものと思われます。」
なんという、物分りのよさだ。
オランダに本拠地を置くRabobankのメンバーが、現在、アメリカ不在で、日本の牛肉市場を、ほぼ独占しているオーストラリアの農業に関する報告書で、以下のサイトのように、次のようにいっている。
「SPS 協定をベースにした牛肉貿易制限は、ますます、不公平になりつつあリ、それは、「擬似的貿易障壁」となりつつつある。是は、将来、オーストラリアに対しても適用されるであろう。
これらの制限は、WTOの精神にはないものだ。
WTOの元でのSPS 協定の存在は、ますます、疑問視されてきている。
衛生上や技術的な制限という形での保護貿易政策は、普通の国際的貿易障壁とのみわけが、ますます、つかなくなっている。
これまで、SPS 協定との協調のもとで国際標準を設定することに、各国とも、気乗り薄である。
政治的経済的思惑が、SPS にもとづくリスク評価を凌駕することがしばしばある。』といっている。
参照
「Report highlights threat to beef exports」
http://www.theage.com.au/news/Business/Report-highlights-threat-to-beef-exports/2005/02/13/1108229852859.html?oneclick=true
アメリカが、カナダを初のthe minimal-risk regionとする『Final rule』を提出するまでの経緯については、次のサイトをご参照
http://www.nationalaglawcenter.org/reporter/registerdigest/aphis/
68 Fed. Reg. 2703 (January 21, 2003) (advanced notice of proposed rulemaking) (to be codified at 9 C.F.R. Ch. I).
The Animal and Plant Health Inspection Service is soliciting public comment to help it develop approaches to control the risk that dead stock and nonambulatory animals could present as potential pathways for the spread of bovine spongiform encephalopathy, if that disease should ever be introduced into the United States.
68 Fed. Reg. 31939 (May 29, 2003) (interim final rule) (to be codified at 9 C.F.R. Parts 93 and 94).
The Animal and Plant Health Inspection Service is proposing to amend the animal importation regulations to prohibit the importation of Holstein cross steers and Holstein cross spayed heifers from Mexico. The regulations currently prohibit the importation of Holstein steers and Holstein spayed heifers from Mexico due to the high incidence of tuberculosis in that breed, but do not place any special restrictions on the importation of Holstein cross steers and Holstein cross spayed heifers from Mexico. Given that the incidence of tuberculosis in Holstein cross steers and Holstein cross spayed heifers from Mexico is comparable to the incidence of tuberculosis in Holstein steers and Holstein spayed heifers, this action is necessary to protect the health of domestic livestock in the United States.
68 Fed. Reg. 2703 (January 21, 2003) (advanced notice of proposed rulemaking) (to be codified at 9 C.F.R. Ch. I).
The Animal and Plant Health Inspection Service is soliciting public comment to help it develop approaches to control the risk that dead stock and nonambulatory animals could present as potential pathways for the spread of bovine spongiform encephalopathy, if that disease should ever be introduced into the United States.
68 Fed. Reg. 62386 (November 4, 2003) (proposed rule) (to be codified at 9 C.F.R. Parts 93, 94, and 95)
The Animal and Plant Health Inspection Service is proposing to amend the regulations regarding the importation of animals and animal products to recognize a category of regions that present a minimal risk of introducing bovine spongiform encephalopathy into the United States via live ruminants and ruminant products, and are proposing to add Canada to this category. It is also proposing to allow the importation of certain live ruminants and ruminant products and byproducts from such regions under certain conditions.
69 Fed. Reg. 10633 (March 8, 2004) (proposed rule) (to be codified at 9 C.F.R. Parts 93, 94, and 95).
The Animal and Plant Health Inspection Service is reopening the comment period for its proposed rule that would amend the regulations regarding the importation of animals and animal products to recognize, and add Canada to, a category of regions that present a minimal risk of introducing bovine spongiform encephalopathy into the United States via live ruminants and ruminant products.
69 Fed. Reg. 42287 (July 14, 2004) (proposed rule) (to be codified at 9 C.F.R. Parts 50, 51, et al.)
Following detection of bovine spongiform encephalopathy (BSE) in an imported dairy cow in Washington State in December 2003, the Secretaries of the U.S. Departments of Agriculture and Health and Human Services announced a series of regulatory actions and policy changes to strengthen protections against the spread of BSE in U.S. cattle and against human exposure to the BSE agent. The Secretary of Agriculture also convened an international panel of experts on BSE to review the U.S. response to the Washington case and make recommendations that could provide meaningful additional public or animal health benefits. The purpose of this advance notice of proposed rulemaking is to inform the public about the panel’s recommendations and to solicit comment on additional measures under consideration based on those recommendations and other considerations.
69 Fed. Reg. 43800 (July 22, 2004) (notice).
This notice announces the Animal and Plant Health Inspection Service’s intention to request an extension of approval of an information collection in support of regulations that restrict the importation of certain animal materials and their derivatives, and any products containing those materials and derivatives, to prevent the introduction of bovine spongiform encephalopathy into the United States.
70 Fed. Reg. 554 (January 4, 2005) (notice).
The Animal and Plant Health Inspection Service is advising the public that it has prepared an environmental assessment relative to a final rule published in today’s issue of the Federal Register to amend the regulations regarding the importation of animals and animal products to recognize, and add Canada to, a category of regions that present a minimal risk of introducing bovine spongiform encephalopathy into the United States via live ruminants and ruminant products. The rule also sets out conditions under which certain live ruminants and ruminant products and byproducts may be imported from such regions.
为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
 Translate
Translate
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2005/03/11 Friday
2005/03/11(Fri)
 対日経済制裁を片手に日本に対して、牛肉貿易再開圧力をかけるのもいいんですけれども、私のブログ「米牛肉交渉、対日制裁の裏舞台をのぞけば?」 http://www.sasayama.or.jp/wordpress/index.php?p=236
対日経済制裁を片手に日本に対して、牛肉貿易再開圧力をかけるのもいいんですけれども、私のブログ「米牛肉交渉、対日制裁の裏舞台をのぞけば?」 http://www.sasayama.or.jp/wordpress/index.php?p=236
にも書きましたように、ポイントは、カナダに適用しようとした「最小リスク規則(the minimal-risk rule)」ならびに「最小リスク地域(minimal-risk regions)」の概念が、アメリカ議会自らによって否定されてしまっているということが、そもそものボタンの掛け違いなんですね。
本来は、アメリカの思惑としては、
1.この「最小リスク規則(the minimal-risk rule)」ならびに「最小リスク地域(minimal-risk regions)」の概念を、手始めにカナダに適用し、
2.カナダからの生体牛輸入によって、この概念を認知させ、
3.それでもって、今度は、アメリカ自体が、OIEのガイドラインに準じて、「最小リスク規則(the minimal-risk rule)」ならびに「最小リスク地域(minimal-risk regions)」の対象地域とみなされ、
4.その上で、日本からの牛肉貿易再開が可能となり、
5.そして、その上で、OIE総会において、この「最小リスク規則 (the minimal-risk rule)」ならびに「最小リスク地域(minimal-risk regions)」の概念を、世界標準として認知させ、米国を「暫定正常国」扱いで認知させるルール作りをし、
6.その上で、今年の7月に、日本との科学的協議によってBEVプログラムの再検討を行い、これによって、カットオフ月齢を昨年10月合意の月齢20ヶ月未満というのを、月齢30ヶ月未満に後退させる、
という手はずだったわけですよね。
ですから、アメリカが、カナダとの国境を封鎖したまま、日本に対して、開国を迫るというのは、上記の「最小リスク規則(the minimal-risk rule)」「最小リスク地域(minimal-risk regions)」のドミノ的認知の過程を、カナダの段階ですっ飛ばしていることからすれば、まったく、理不尽の圧力なわけですね。
この辺を、もう少し、詳しく見てみましょう。
昨年12月29日に、アメリカUSDAは、BSE ミニマルリスク規則を発表しました。
そのころは、日本では、すでに正月ムードで、誰も、注目しませんでしたけれども。
この規則作成の過程で、USDAが行った広範囲なリスクアセスメントでは、カナダでさらにBSE 例が発見される可能性を考慮に入れています。
OIEのガイドラインによりますと(この辺の関係は、リンクが時系列的に後先になってしまいますけれども、こちらhttp://www.sasayama.or.jp/wordpress/index.php?p=242のブログ記事をご覧になってくださいね。)、過去4 年間連続、24 ヶ月齢以上の牛100 万頭あたり2 頭以下の発症国はミニマルリスク国となり、カナダの場合、24 ヶ月齢以上の牛が550 万頭いますので、BSE 対策や予防措置が効果的に行われている限り11 頭まではミニマルと考えられています。
http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome?contentidonly=true&contentid=2005/01/000
1.xml ご参照
このミニマル・リスク規則にもとづいて、USDA がBSE のミニマルリスク地域を規定する規則を発表し、ここで、カナダをミニマルリスク地域と規定することによって、カナダから米国への牛肉の輸入を可能としたのです。
このうえで、USDA は12 月29 日、効果的なBSE 予防対策および検出システムがある地域からの30ヶ月齢以下の生きている牛及びその他の製品の輸入を可能とする条件を規定する規則を公表しました。
このアプローチについて、USDAは、「OIE のガイドラインに沿ったもので、適切な科学に基づくリスクmitigation 対策に基づくものである。リスクアセスメントの結果、カナダがこのミニマルリスクエリアに初めて指定されものである。」との見解を発表しています。
にもかかわらず、大統領の拒否権発動という可能性は残されてはいますが、カナダからの生体牛の輸入阻止を目的とした、「カナダとの生体牛貿易再開に反対する議案(.J.RES.4 Providing for congressional disapproval of the rule submitted by the Department of Agriculture under chapter 8 of title 5, United States Code, relating to risk zones for introduction of bovine spongiform encephalopathy.」が、上院で、賛成52.反対46で、可決されたのですね。
このことは、何を意味するかといえば、USDAが12月29日に発表した、「最後の規則−ファイナル・ルール」とする、ミニマル・リスク規則とミニマルリスク地域を規定する規則を、アメリカ上院議会自らが、否定したということなんですね。
このままでは、アメリカにとって、カナダが、ミニマルリスク地域でないばかりでなく、日本にとっても、アメリカがミニマルリスク地域でないという理屈になりますね。
つまり、たとえ、日本が、アメリカの理屈に最大限沿ったとしても、アメリカがミニマルリスク地域とならない限り、アメリカは、日本に対して、牛肉を輸出できないことになりますね。
それなのに、どうして、日本がアメリカから、牛肉輸入の開国要求圧力を受けるのか、私には、その意味が、さっぱりわかりませんね。
日本のマスコミは、このカナダと日本との関係について、まったく記事を書かないのですが、まさに、この問題のポイントは、カナダの開国によって、「最小リスク規則 (the minimal-risk rule)」ならびに「最小リスク地域(minimal-risk regions)」の概念が認知されるかどうかの問題にあるわけです。
そこが認知されさえすれば、後は、なし崩し的に、という方向なんですね。
もし、日本の食品安全委員会が、アメリカからの直接的、間接的圧力の下で、月齢20ヶ月未満の安全性にゴーサインを出すということは、結果的に、このカナダにも適用されていない、「最小リスク規則 (the minimal-risk rule)」ならびに「最小リスク地域(minimal-risk regions)」の概念を、世界に先駆けて認知してしまうと言うことになりかねないのです。
その点は、日本の食品安全委員会も、そのことの重大さについて、認識していただきたいものですね。
「アメリカは、カナダ生体牛輸入問題を解決してから、日本に圧力をかけるべし。」このことを、アメリカの議会の皆さんにも、声を大にして言いたいのです。
それと、もうひとつ、CAFTAのアメリカ議会承認の代償として、日本に対して、牛肉貿易再開を求める動きがあるというのも、理不尽な話ですね。
米国政府が中米5ヵ国(コスタリカ、ホンジュラス、エル・サルバドル、グアテマラ、ニカラグア)との自由貿易協定(CAFTA)がようやく妥結して、ブッシュ政権は、アメリカ議会の承認に持ち込みたい考えのようですが、ここにきて、アメリカ国内においても、米国以外のCAFTA加盟国でも、批准反対論が噴出しているようです。
それは、CAFTAと同じ考えでやってきたNAFTA(北米自由貿易協定 アメリカ カナダ メキシコ)が、今のカナダとの生体牛貿易問題にみるごとく、それほど効をなさかったという反省の上にたってのことなのでしょうね。
とくに、購買力のないメキシコの加盟は、アメリカにとっては、雇用の域内輸出入に過ぎなかったという、思いもあるのでしょう。
また、アメリカ国内砂糖業者にとっては、CAFTA加盟によって、新たな競争者が現れることになります。
特に投資家保護をあまりにもあらわに出しすぎた、現在のNAFTA協定にあるChapter 11条項というものが、CAFTA協定にも適用されるのではないかという疑心暗鬼があるのではないでしょうか。
つまり、CAFTA加盟国が、投資家保護に違反した場合は、Chapter 11条項をもとにしての、国を相手取っての訴訟合戦がはじまるというわけです。
加盟国内の一企業が、何らかの政策決定によって利益を損なわれた場合には、他の加盟国の政府に対して、訴訟をおこしうるという、条項ですね。
そこで、ブッシュ政権が、CAFTA協定を議会に承認してもらうための道連れに選んだのが、「日本とのアメリカ牛肉貿易再開問題」であるといえるのではないでしょうか。
CAFTAは、アメリカにとっては、市場にならないが、日本という牛肉市場に風穴をあければ、何とか、議会も、まるく収まるだろうという思惑なのでしょう。
とんだアメリカ議会の取引材料に、日本の牛肉貿易再開問題が使われたものです。
もっとも、アメリカの消費者団体であるパブリックシチズンは、以下のサイト http://www.citizen.org/pressroom/release.cfm?ID=1883で、こういつていますね。
「カナダの畜産業者たちが、アメリカの国境封鎖による損害補償を、NAFTA協定のChapter 11条にもとづいて、膨大な金額を請求してくるであろうし、これが、NAFTA+CAFTAともなれば、両加盟国からのアメリカ政府に対する補償請求は、ますます、莫大な額になるであろう。結局、それらの補償費の国の負担は、消費者にかぶさってくるのだ。」といっていますね。
つまり、日本の牛肉貿易再開をトレードオフにして、CAFTAの議会承認をしたところで、将来、CAFTA加盟国についても、今回のNAFTA加盟国であるカナダの牛肉問題のような問題が多発して、結局は、アメリカは、Chapter 11条的条項にもとづいたCAFTA加盟国からの膨大な補償問題が発生すれば、何にもならないじゃないか、という視点ですね。
日本政府も、この辺のアメリカのお国の事情をよくわきまえた上で、対日経済制裁にたいし、きっちり対応するようにしないと、いけませんね。
 Translate
Translate
-HOME-オピニオン-提言-情報・解説-発言-プロフィール-図書館-掲示板-
238
 4月11日、カナダの十万人の畜産業者たちが、カナダ政府を相手取って、七十億ドルの損害賠償を求め、集団訴訟した。
4月11日、カナダの十万人の畜産業者たちが、カナダ政府を相手取って、七十億ドルの損害賠償を求め、集団訴訟した。 Translate
Translate どうも、日本人の性格として、国際基準などとなると、律儀に守らなければならないような感じにとらわれるのだが、OIE基準をめぐる輸出国・輸入国の思惑は、もっと娑婆臭いものようだ。
どうも、日本人の性格として、国際基準などとなると、律儀に守らなければならないような感じにとらわれるのだが、OIE基準をめぐる輸出国・輸入国の思惑は、もっと娑婆臭いものようだ。 先に述べた北米三国(カナダ・メキシコ・アメリカ)の統一BSE対策の詳細がわかりました。
先に述べた北米三国(カナダ・メキシコ・アメリカ)の統一BSE対策の詳細がわかりました。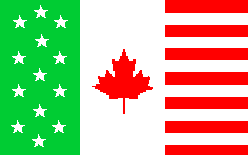 「米国、カナダ、メキシコは1日、食肉からの脳や眼球など特定危険部位の除去や、感染源となり得る肉骨粉飼料の禁止など、9項目の最低基準を満たせば域内の牛肉貿易を認めることを柱とする3カ国統一の牛海綿状脳症(BSE)対策を策定したと発表し、これをOIEの改正会議で国際統一ルールとするように働きかけるとのことである。
「米国、カナダ、メキシコは1日、食肉からの脳や眼球など特定危険部位の除去や、感染源となり得る肉骨粉飼料の禁止など、9項目の最低基準を満たせば域内の牛肉貿易を認めることを柱とする3カ国統一の牛海綿状脳症(BSE)対策を策定したと発表し、これをOIEの改正会議で国際統一ルールとするように働きかけるとのことである。 アメリカ通商代表部は、今日発表された「National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE)」に関する報告書の(題名は、「The National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers」)の中で、日本の牛肉貿易障壁について記述している。
アメリカ通商代表部は、今日発表された「National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE)」に関する報告書の(題名は、「The National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers」)の中で、日本の牛肉貿易障壁について記述している。 R-CALFの最高執行者Bill Bullard氏が、声明を出したが、その中で、現在の日米の牛肉問題について、次のようにいっている。
R-CALFの最高執行者Bill Bullard氏が、声明を出したが、その中で、現在の日米の牛肉問題について、次のようにいっている。
 米国は3月9日に開かれた世界貿易機関(WTO)動植物検疫措置(SPS)協定に関する会合で、日本に米国産牛肉の輸入再開を正式に求めたというのだが。
米国は3月9日に開かれた世界貿易機関(WTO)動植物検疫措置(SPS)協定に関する会合で、日本に米国産牛肉の輸入再開を正式に求めたというのだが。 対日経済制裁を片手に日本に対して、牛肉貿易再開圧力をかけるのもいいんですけれども、私のブログ「米牛肉交渉、対日制裁の裏舞台をのぞけば?」
対日経済制裁を片手に日本に対して、牛肉貿易再開圧力をかけるのもいいんですけれども、私のブログ「米牛肉交渉、対日制裁の裏舞台をのぞけば?」