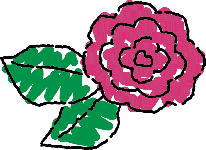 パリの南60㎞にあるフォンテーヌブローの森の西側に接して、バルビゾンという村があります。
パリの南60㎞にあるフォンテーヌブローの森の西側に接して、バルビゾンという村があります。
この村に画家たちが住みつき始めたのは19世紀の初めでした。
今でも、村の入口には「画家たちの村・バルビゾン」という看板が立っています。
この村からは、ルソー、ミレーなど、いわゆるバルビゾン派と言われる、自然を描いた多くの画家たちが巣立っていきました。
田園に飛び出した画家たち
この画家たちをして自然を描くことに目覚めさせたのは、イギリスの風景画家ジョン・コンスタブル (1776~1837) が描いた「干草車」という1枚の絵です。
それまでのフランスの風景画は、必ず英雄や神々や妖精が登場していましたが、コンスタブルの絵には、ただ数頭の牛に干し草を積んだ車を引かせ、浅瀬を渡っていく農夫の姿があるだけでした。
フランスの画家たちは、この絵に風景画の新しい無限の可能性を見いだし、自然の真の姿を描くために田園に飛び出していきました。
当時のパリは産業革命が進行中で、これまで慣れ親しんできた自然は次々と消えつつありました。
コンスタブルの絵に刺激された、バルビゾン村の画家たちは、自然の消滅に抵抗するかのように、あらゆる自然の断片を、むさぼるように農村や田園の中に捜し、それを自らの絵の中に取り入れていきました。
それは、まるで田園景観の標本づくりに精を出す求道者のようでした。
フランスの画家たちに大きなインパクトを与えたコンスタブルも、母国イギリスでの評価は芳しいものではありませんでした。
特に、当時のイギリスの画壇に影響力をもつラスキンの辛辣な批判は、コンスタブルのイギリスでの評価をいっそう低いものにしました。
同じ風景画家ターナーをことのほか評価したラスキンは、その反動として他の風景画家をおとしめる評価をしました。
ラスキンは、コンスタブルの絵は効果的でない彩色がされているとして、その著『近代画家論』の中で完全に無視しています。
 当時の風景画には、絵の前景に必ず古いヴァイオリンの色のような褐色が塗られていたのに、コンスタブルはその色を用いなかったのです。
当時の風景画には、絵の前景に必ず古いヴァイオリンの色のような褐色が塗られていたのに、コンスタブルはその色を用いなかったのです。
コンスタブルは、あるとき古いヴァイオリンを持ってきて芝生の上に置き、新鮮な緑と褐色がどんなに違うかを見せたといわれています。
また、木の茂みや草に輝く光を描くため、緑色の上に白い絵の具を重ねたところ雪のように見えたため、「コンスタブルの雪」と冷笑されたこともありました。
このような従来の絵画技法を重んじる人々からの嘲笑にもかかわらず、コンスタブルは当時の画家としては初めて、戸外に直接画架を立て、科学者の態度で自然と対峠し、自然の法則を見きわめようとしました。
ターナーの描く絵の世界が想像の理想美に満ちた世界だったのに対し、コンスタブルのそれは、自然が語りかけるメッセージに素直に従った世界を描いたものでした。
コートと雨傘を思いださせる絵
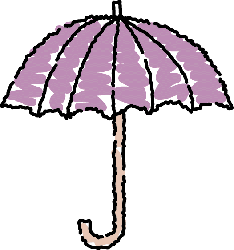 イギリスでの風景画家の社会的地位は、宗教絵画や歴史画、肖像画のそれに比べて著しく低いものでした。中世において、風景は単にキリストや聖母、人物の背景にチラリと描かれるにすぎませんでした。
イギリスでの風景画家の社会的地位は、宗教絵画や歴史画、肖像画のそれに比べて著しく低いものでした。中世において、風景は単にキリストや聖母、人物の背景にチラリと描かれるにすぎませんでした。
英国において、自然の風景そのものが絵画の対象となるのは、17世紀のオランダ風景画の誕生の影響を受けてからのことです。
18世紀に入り、イタリアの画家カナレットが英国に渡り、風景そのものを題材にした絵を描くに至り、ようやく風景画としての社会的地位が確立したのでした。
それでも風景の対象は、町並みや邸宅、古代の遺跡、遺物など、いわゆる名所図会的な風景にとどまり、山や森、湖、川などの自然が対象となるのは18世紀の中頃になってからのことです。
風景画の社会的地位が低いばかりに、風景画家たちは、かえって己の技術を誇示しようと、写生によって集めたさまざまな自然を、アトリエで再構成し、生の自然をいわゆる美しい自然に変えることに没頭しました。
そして生の自然は、彼らの手によって、より牧歌的な風景に歪曲され、産業革命の中でより困窮な立場に陥りつつあった農村の原風景とはますます異なる、ギャップと幻滅を生みだすのです。
18世紀を代表する英国の風景画家ターナーにしても、そのトートロジーから逃れることはできませんでした。
彼は、当時のピクチャレスク (絵のように美しい) な絵画を構成するための小道具として、自然を見ているにすぎなかったようです。
身近な自然を描くというよりは、ヨーロッパ各地を旅行し、その各地での際立った風景を絵の題材としていました。
コンスタブルは、それとは対象的です。
彼は一歩も英国を出ることなく、しかも、少年時代から慣れ親しんだサフォーク州周辺の四季の風景ばかりでなく、1日の朝昼晩の変化、さらには気象学者のような厳格さをもって、一瞬一瞬の気象の変化に伴う風景の変化を克明にキャンバスに描き下ろしていきました。
彼の絵の中には、スケッチした時の風向きなどが記されたものもあります。
コンスタブルにとって大切なのは、光や風や雲とともに変化する真の自然でした。
そして、その中で生業を営む農民の息づかいでした。彼の絵を見た画家フッセリが、「彼の絵を見ていると戸外に立っているような気がして、いつもコートと雨傘を思い出させる」と、語ったというエピソードもあります。
こうして、コンスタブルの「当たり前のことを当たり前に」描く画法によって、多くの画家たちは長年の催眠術から解き放たれたかのように、自然を動きまわり真の自然の姿を確認しようとしたのです。
自然を科学的にとらえた絵
一方、日本においても、日本の原風景をとどめることに情熱を燃やした画家がいました。
大下藤次郎です。
日本における風景画は、明治20年代後半から、水彩画による絵葉書ブームというかたちで興こりました。
時あたかも日清戦争から日露戦争にかけての時代で、戦地に赴く一家の主への通信に、望郷の念をおこさせる日本の風景を印した絵葉書が使われていたのです。
同時に植物学・昆虫学・地学の発達とともに、自然を科学的にとらえる人々も出てきました。
五百城文哉もその1人です。
五百城は、農商務省山林局で標本を描く仕事を担当しながら画を学んだ人で、明治34(1901)年に日光を訪れた牧野富太郎とともに植物採集をしたのが縁で、牧野の仕事を手伝い「日本高山植物写生図」などを残した特異な人です。
五百城の描く「百花百草図」は、絹の上に水彩で描かれたもので、残雪の高山の岩場に張りつくユリ、キキョウなどの植物の絵が描かれています。
このように、これまでの花鳥図が植物画に、絵葉書の名所絵が風景画になるちょうど端境期に、大下藤次郎は風景画による水彩画家となることを決意します。
明治29(1896)年、コンスタブルの「干草車」発表に遅れること、約70年後のことでした。
人と自然が描かれた絵
「我は如何にして画家となりしか」という文の中で大下自身、風景画家となるのを決意したきっかけについて次のように語っています。
「当初、父の友人である中丸精十郎について画を学ぼうとしたが、中丸は肖像画の専門家なので、中丸氏が没したのを期して原田直次郎の門下に入り、そこで三宅克己と出会った。
三宅も水彩画を専門としようと志ざしていたので、それに倣った」と。
そして、大下の描く風景画に大きな変化をもたらしたのが、明治31年のオーストラリア旅行でした。
ブリスベン、シドニーやメルボルンの美術館に立ち寄った際、葉の原薄や枝のしなりぶりまで克明にかかれた風景画に出会い、ショックを受けます。
ここで、江戸時代からの踏襲を濃く引きずっていた絵画観が、一挙に大下の中から遠のいていきます。
友人の三宅克己も、日本で明治27年に開催されたアルフレッド・パーソンズの水彩画展に刺激され、明治31年米国を経てイギリスに渡ってパーソンズを訪問しています。
2人は帰国後、別々の地で日本のバルビゾン村を築こうと決意し、大下は青梅に、三宅は信州に居を構え、製作に専念する日々が続きました。この当時の大下の絵の中には、必ず風景の片隅に人間が小さく描かれています。
私の好きな「秋の雲」(1904 年作) という絵の中には、日傘をさした女性とその連れが小さく描かれ、そのことが自然のもつ恐ろしさと淋しさを和らげ、風景と人間との共生感を生みだしているように思えます。
画架をかついで山に登る
当時、大下が親交を結んでいた人々の中に、志賀重昂と小島烏水がおりました。
志賀の著した『日本風景論』は、日本の風景観の先駆けをなすとともに、近代登山の諸技術を紹介した名著です。
大下は、遠洋航海から帰ったばかりの志賀の話を聴くため、たびたび彼を訪ねていました。おそらく志賀の風景観が、大下の風景を見る思想に大きく影響を及ぼしたに違いありません。
一方の小島烏水は、志賀重昂のよきライバルでした。
志賀の『日本風景論』の一部に、ガルトンの著からの引用が多いのをいち早く読み取り、間接的にたしなめたのも小島でした。
大下は水彩画講習所を設けるため、各界に寄付を求めて奔走していた時に小島と知りあいます。
そして、小島と知己を得たのをきっかけに、大下は当時小島が設立に努力した「日本山岳会 (山岳会の後身) 」に入会します。
入会後、大下は上高地、穂高、木崎湖、青木湖などを旅行することが多くなり、したがって描く絵も山岳風景が多くなっていきます。
当時は上高地といっても、現代からは想像もできぬ未踏の地でした。
登山姿で画架をかつぐ大下の姿には、産業化への足音が聞こえだした今こそ日本の風景を採集しておかなければならない、という使命感に満ちたものが感じられます。
80年前の画家が残したメッセージ
こうして、戸外に画架を構え、自然と直接対峙するという大下の風景画家としての姿勢は、晩年まで貫き通されました。
しかし、小島烏水との接触により、大下の心の中に、自然を通して人生を見る諦観に似た感情が生じ、それが大下の絵の中にも現れてきたようです。
晩年の山岳風景を中心とした作品には、かつての青梅時代のような人物の姿は消え去り、すばらしいけれども、人を寄せつけぬ冷たさがただよってくるようになりました。
それは、大下自身の身体の衰えがそうさせたのかもしれません。
明治44(1911)年、大下は41歳の若さであっけなく世を去りました。大下が世を去ると、日本の水彩画ブームもしぼんでいきました。
また、大下がこよなく愛した日本の風景は、産業化への嵐に襲われていきました。
大下が身体を酷使して採集した日本の風景の断片は、プレパラートのごとく残されたままです。
しかし、この断片は、大下没後80余年たった今でも、瑞々しく、私たちの心のある部分に語りかけてきます。
そして日本の風土のもつ原風景とは何なのか、風景と人間とが共生できる土壌とは何なのかを、私たちに問いかけてきます。
日本の原風景がリゾート的修景によって、汚く塗り直されつつある今日、私たちは大下が寡黙のうちに残したメッセージを、後世に語り継ぐ責任を負わされているような気がします。
|  田園を勇気づけた人々
田園を勇気づけた人々 田園を勇気づけた人々
田園を勇気づけた人々 早すぎた田園主義者「宮沢賢治」と「松田甚次郎」
早すぎた田園主義者「宮沢賢治」と「松田甚次郎」 田園散策のナチュラリスト「H・D・ソロー」
田園散策のナチュラリスト「H・D・ソロー」 はるかなる先見者「ウィリアム・モリス」
はるかなる先見者「ウィリアム・モリス」 郷土のエネルギー発現を目ざした「新渡戸稲造」と「柳田国男」
郷土のエネルギー発現を目ざした「新渡戸稲造」と「柳田国男」 風土の力に光をあてた「ラッツェル」と「三沢勝衛」
風土の力に光をあてた「ラッツェル」と「三沢勝衛」 みちのくの鳥のファーブル「仁部富之助」
みちのくの鳥のファーブル「仁部富之助」 田園の魅力を生涯追求した「天野藤男」
田園の魅力を生涯追求した「天野藤男」 消えゆく田園風景を描き続けた「コンスタブル」と「大下藤次郎」
消えゆく田園風景を描き続けた「コンスタブル」と「大下藤次郎」![[戻る]](back.gif)
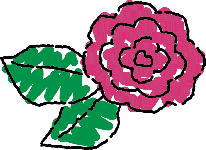 パリの南60㎞にあるフォンテーヌブローの森の西側に接して、バルビゾンという村があります。
パリの南60㎞にあるフォンテーヌブローの森の西側に接して、バルビゾンという村があります。