 「環境」と「風土」という言葉には、微妙な違いがあります。
「環境」と「風土」という言葉には、微妙な違いがあります。
前者は人間を中心に据え、その周辺の人間の生存可能な条件を整えるというニュアンスが強いのに対し、後者は人間も、人間と共生する野生生物や景観も、互いの働きかけによって相互に生存条件を満たす状況をつくっている、という違いとでもいえましょうか。
ヨーロッパにおけるヘルダー、リッターらの考えを受け継いで発展させ、人間は自然に対してどのような文化的働きかけができるかを説いたのが、ラッツェルです。
ラッツェルの「国家有機体説」
フリードリッヒ・ラッツェルは、1844年8月30日、南ドイツ・バーデンのカールスルーエに生まれました。
幼い頃から植物採集が好きな子供でしたが、15歳から4か年の間、薬剤師の所で見習い生活を送ったのをきっかけに、自然科学の分野に興味をもっていきます。
66年カールスルーエの工芸学校に入学したラッツェルは、ヴィッテルのもとに師事し、地質学や古生物学を学びました。
工芸学校卒業後、69年にケルン新聞の記者となったラッツェルは、記者としてベルリンなどを訪れる機会を得、さらに70年には普仏戦争における特派員として前線に赴き、終戦後はサクセン、ハンガリーなどに、また73年から2年間はアメリカ旅行という、相次ぐ旅を経験します。
この過程で、ラッツェルの心の中には「地と人との関係」を探る思索の種が芽生えていきました。
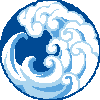 75年、中国人移民に関する論文を書いたことがきっかけで、翌年ミュンヘン王立学校の教授となり、地理学者としての道を歩み始めます。
75年、中国人移民に関する論文を書いたことがきっかけで、翌年ミュンヘン王立学校の教授となり、地理学者としての道を歩み始めます。
世界がラッツェルに名実ともに注目しだしたのは、彼の著した『ドイツ−郷土学入門』と『人文地理学』です。
もともと動物学者であったラッツェルは、地理学に生物地理学的方法を駆使し、動物と環境との関係を論ずるのと同じように、人間と環境との関係を論ずることが必要であると説きました。
そして、動物と人間との大きな差異は、人間は動物と違って大規模な移動ができる点だということに注目しました。
1個体として発生した人間が、移住に移住を重ね、今日の民族分布に至っている以上、その移動を促した環境の変化やその時の人間自身の特性の変容にも注目しなければならないというのです。
ラッツェルは、移動の過程において人間自身がその場所ごとに生み出した文化の発達は、その場所の自然をいっそう深く利用する方向に動いているとし、人間自身の自然に対する文化的な働きかけが、自然そのものの変容をもたらすと結論づけたのでした。
ラッツェルの考え方は、リッターやヘルダーの「人間が一方的に環境によって規定される」という考え方から一歩出て、「人間自身が土地利用という文化的な働きかけによって自然と新たな関係を結ぶ」という見解に進んだことに大きな意義があります。
ラッツェルにとって不幸なことは、第1次大戦敗戦と、苛酷なヴェルサイユ条約のもとに反発するドイツ民族主義の高まりと、ヒットラーの台頭でした。
人と土地との関係を説いた「国家有機体説」というラッツェルのテーマは、ドイツ民族の優越性を示すのに、まことに有力な理論的武器となってしまったのです。
こうしてラッツェルの真に目指した意図は歪曲され、ラッツェルの再評価は、第2次大戦直後の動乱が安定した時期にもち越されたのでした。
土地の「風土計」を見る
 一方、日本においても、風土のもつ力を積極的に評価し、農業の生産力向上に結びつけようとした実践家がいました。三沢勝衛です。
一方、日本においても、風土のもつ力を積極的に評価し、農業の生産力向上に結びつけようとした実践家がいました。三沢勝衛です。
明治18(1885)年、長野県に生まれた三沢勝衛は、地元の諏訪中学で地理を教えるかたわら、県内や県外の農業・産業と風土のかかわりを確かめるために綿密な観察を続けてきました。
昭和11(1936)年、長野県伊那郡の青年講習会に招かれた三沢は、風土の力を生かした産業と地方振興のあり方を講義します。
この時の講演を基調にした『風土産業』という本は、昭和16年に信濃教育舎から信州の青年に向けて刊行されました。
「草も語る、木も語る、いな草木鳥獣、皆語る。大自然の持つ真相を」との言葉から始まるこの書は、三沢没後50年以上を経た今日、なお新鮮な感動を私たちに与えてくれます。
三沢は、風土を大自然である大地の表面と大気の底面との接触面における一大化合体であるとし、この接触面において土壌・植物・動物・人間が互いに大地・大気と関係しあいながら、一体となって表出するものであるとしました。
そして、我々が風土を具体的なかたちで知るものとして、さまざまな「風土計」ともいうべきものがあって、例えば植物の生長・繁茂は風土の一表現であり、我々人類は、風土計たりうる植生・動物・土壌・人類の生活を深く細かく調査研究し、そこから発見することが必要であるとしました。
常風を知るには樹冠がどの梢に傾いているかを見ればよいし、空中の湿度を知るにはスギコゲやサルオガセの生え方を見ればよい、気温を知るには自然の寒暖計であるヒガンザクラの開花期やケヤキの発芽の状態などを見ればよいというのです。
さらにある地域の風土を調べるには、そこの風土を鋭敏に正確に表現している指針植物・指針動物に注目する必要があるとしました。
その場合も単に今、生長・繁茂している種のみではなく、前時代の種を確認し、次の時代にあり得る種を想定し、風土を空間的にも時間的にも観察する必要があるとしています。
風土を活用した農業
三沢は風土の観察にとどまらず、風土を活用することこそ人類の叡智であるとし、低温、多雪、冷水、風が強い、低湿など、一見望ましくない自然に対しても、それを憎んだり、征服したりしようとするのではなく、風土に従い、その力を活用することでプラスの力が生まれるとしました。
具体例として、低温を活用した穂高のワサビ、諏訪の寒天、雪を活用した山形のユキナとラミー、信濃川沿岸のチューリップ、冷水を活用した柏原の鍋や錆江の鍛冶工業、長野のホウレンソウ、低湿を活用した菅平高原のジャガイモ、佐久高原のフリージア、風を活用した夏秋蚕飼育、ササゲ、ウルシの防風林などをあげています。
三沢の基本的なスタンスは、自然に善悪は無く、ヤセ地といえども、それを活用することはできるということにありました。
農業についても、近頃の農業があまりに人工化されていることに警告を発し、あかたも人工的に作物の生育条件をコントロールすることが、農業の近代化の指標とされているのは大いに問題であり、長続きするものではないとしています。
また、農業にいかに有価値・無価格の風土を折り込むかが、農業のコストを下げ、その地ならではの特色ある農作物をつくる原動力になるとしました。
この指摘はそのまま現代の近代農業に対してもつながるものであり、今、改めて傾聴すべきものでしょう。
このように三沢勝衛は、ラッツェルのいう「人間自身の自然に対する文化的働きかけ」を具体的な実践活動として、ありのままの自然や風土を地域振興の戦略に位置づけたことに大きな意義があります。
三沢は、絶筆『新地理教育論』を残し、昭和12年52歳で逝去しましたが、第2次大戦後の食糧難を克服するためのアメリカ寄りの近代農業の導入は、日本の農と風土と景観を変えてしまいました。
ポストモダンの農を考えざるを得ない現在、風土に光を当てた三沢の努力は、いま再認識され実践に移される機会を得ているのではないでしょうか。
|  田園を勇気づけた人々
田園を勇気づけた人々 田園を勇気づけた人々
田園を勇気づけた人々 早すぎた田園主義者「宮沢賢治」と「松田甚次郎」
早すぎた田園主義者「宮沢賢治」と「松田甚次郎」 田園散策のナチュラリスト「H・D・ソロー」
田園散策のナチュラリスト「H・D・ソロー」 はるかなる先見者「ウィリアム・モリス」
はるかなる先見者「ウィリアム・モリス」 郷土のエネルギー発現を目ざした「新渡戸稲造」と「柳田国男」
郷土のエネルギー発現を目ざした「新渡戸稲造」と「柳田国男」 風土の力に光をあてた「ラッツェル」と「三沢勝衛」
風土の力に光をあてた「ラッツェル」と「三沢勝衛」 みちのくの鳥のファーブル「仁部富之助」
みちのくの鳥のファーブル「仁部富之助」 田園の魅力を生涯追求した「天野藤男」
田園の魅力を生涯追求した「天野藤男」 消えゆく田園風景を描き続けた「コンスタブル」と「大下藤次郎」
消えゆく田園風景を描き続けた「コンスタブル」と「大下藤次郎」![[戻る]](back.gif)
 「環境」と「風土」という言葉には、微妙な違いがあります。
「環境」と「風土」という言葉には、微妙な違いがあります。