郷土のよさ、田園のよさを再認識し、土地と人との結びつきを強化しようという考え方が、18〜19世紀にかけてヨーロッパで興り、これに共鳴する多くの人々の運動を生みだしました。いわゆる「郷土論」の考え方です。
ヨーロッパの郷土論
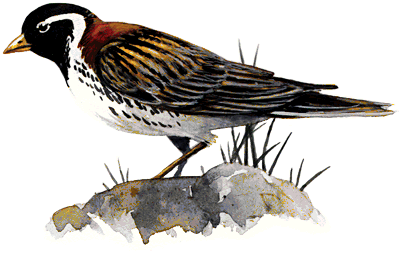 ドイツのメーザーは荒廃する村落を救うべく村落の理想像を探り、ヘルダーは田園の風物や民俗の意義を強調し、風土の思想を提唱しました。
ドイツのメーザーは荒廃する村落を救うべく村落の理想像を探り、ヘルダーは田園の風物や民俗の意義を強調し、風土の思想を提唱しました。
また、ペスタロッチは「地球は人間の教育所である」との理念に基づき、郷土における生活体験に即した教育哲学の確立をはかりました。
リッターは師フンボルトの考えを受け継ぎ、「土地と住民とは最も密接な相互関係にある」として、各地への旅行・探検を通じて地理学の体系化に努めました。
ルドルフは、郷土保護という考え方を提唱し、風土・風景の保護を訴えました。
これら一連の郷土論で興味深いのは、その基本となる哲学に今日でいういわゆる環境論がさまざまな角度から論じられていることです。
自然環境の中での人間の立場はどこにあるのか、その中で人間は自然にどう働きかけられるのか、がこの考え方の柱です。
これらの郷土論を継承、あるいは修正しながら「郷土学」という新しい分野を確立したのはラッツェルでした。
日本に芽生えた「地方学(じかたがく)」
西欧の郷土論を日本に紹介したのは、今でいう「地理学」の初期の学者たちです。
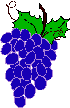 なかでも当時の人々に啓蒙的な役割を果たしたのが、内村鑑三でした。
なかでも当時の人々に啓蒙的な役割を果たしたのが、内村鑑三でした。
内村は明治27 (1899) 年に『地人論』を著し、リッターの考えを引きながら「郷土と政治は、地理学を出発点にして語られなければならない」と説きました。
この考え方は、同じ札幌農学校の新渡戸稲造、柳田国男らを刺激します。
ドイツ留学の経験もある新渡戸は、早くからドイツにおける「郷土保護(Heimat Kunst)」の考え方に共鳴し、都市化の波に揺れる当時の農村が個性をもって自立するためには郷土保護の考え方が必要だと述べていました。
明治31年に『農業本論』を著した新渡戸は、その中で「地方(じかた)学」の必要性を唱え、さらに明治40年の第2回報徳例会の講演で「地方の研究」について自らの考えを詳しく述べることになります。
当時「郷土」という言葉は、今ほど一般的なものではありませんでした。そこで新渡戸は、江戸時代から使われている「地方」の語を使ったのです。
この講演のなかで新渡戸は、このようなことを言っています。
「詩人テニソンは、小さな一輪の花を取って、比花の研究が出来たら、宇宙万物の事は一切分かると言った。
即ち、一葉飛んで天下の秋を知る如く、一村一郷の事を細密に学術的に研究して行かば、国家社会の事は自然と分かる道理である」
「東京近在で地理を教えるにも、富士山とか大井川とか緑の遠いものを教えずに、先ず其村の岩とか、近所の山とかを教え、川なら小川でも可いから、其村を流れて居るものから教えたい。
歴史も其通りで、東洋歴史よりも、先ず村の歴史を教えたい」
これは、今日の環境教育のあり方にも充分適用できる、鋭い指摘でした。
郷土を考える各種の研究会

その時の聴衆の1人に、当時34歳で法制局参事官の若き柳田国男もいたのです。
柳田は新渡戸の考えに触発され、明治40年頃から自宅で「郷土研究会」という名の集まりをもつようになります。
集まってくるメンバーは小田内通敏、牧口常三郎、滝沢敬一、石黒忠篤らでした。
当時、全国の辺地を旅していた柳田は、帰ってきては研究会で自らの考えを含めた旅の話をするのが常でした。
メンバーのなかで小田内通敏は新渡戸と親交があり、その関係から明治43年に小石川小日向の新渡戸邸で、新渡戸を会の後援者、柳田を幹事役として「郷土会」を発足させることになります。
郷土会のメンバーは大きく3つに分かれました。
1つは農改の実践に携わる人(有馬頼寧、石黒忠篤、小野武夫、木村修三、那須晧)、そして地理学に携わる人(小田内通敏、牧口常三郎、正木助次郎)、さらに植物学に携わる人(草野俊助、三宅驥一)です。
この常連10人の他にも多くの人々が参加していました。
郷土会は、各メンバーが自らの関心のあるテーマについて述べるというかたちをとっており、サロン的雰囲気のなかで進められました。
また時には、実地に村落研究をするため、関東近辺の小旅行も試みられました。
こうした自由な運営は新渡戸の人柄とも相まって和気あいあいの空気を醸しだしました。
その反面、各人が話すテーマがバラバラであまりにミクロ的なレベルであったために、郷土会は目的をもった一定の方向には発展しませんでした。
この頃柳田は『郷土研究』という雑誌を創刊 (大正2年3月) するのですが、同誌の性格については純粋の民俗研究の誌とするのか、あるいは地方経済 (の研究を志向するのか、迷っていました。
これに対して友人の南方熊楠は、この雑誌が狭い民俗学のための雑誌にとどまらず、より広義の地方経済についてのものにすべきとの考えを示します。
大正3年5月、柳田へ宛てた南方の書簡には「産業の改変、地境の分劃、市村の設置、水利道路の改善、衛生事業、又、殊には地方有利の天然物を論ぜざるべからず」とあり、まず地方制度のあり方から論を進めるべきだとしています。
しかし、南方の指摘は取り入れられることなく、『郷土研究』は民俗学の専門雑誌という性格を強めていきます。
新たに求められる郷土実践論

このように新渡戸の目ざした「地方学」たる郷土論の展開は、新渡戸の意図とは裏腹にミクロの調査研究にとどまり、より体系的に郷土学を確立するには至りませんでした。
一方、民俗学的なアプローチに固執した柳田も、民俗学の視点からさらにミクロの観点に移行し、農政・地方経済学と民俗学の融合というレベルには至らなかったのです。
大正8年3月、郷土会の中心であった新渡戸が後藤新平とともに欧米視察に出かけ、同年12月に柳田が貴族院書記官長を辞任するのを機に、会は消滅に向かいます。
また、柳田が情熱を燃やした雑誌『郷土研究』も、刊行4年後の第4巻12号をもって休刊となりました。
日本の民俗学が、他の学問のように、西欧のものまねからスタートすることなく、日本独自の道をたどったことについては評価すべき点もありました。
しかしその反面、西欧の「郷土学」のように総論として体系づけられることなく終わってしまい、地方の時代と叫ばれる現在に至っても、地方活性化のための具体的戦略の根拠たり得ていないことは、不幸な出発であったともいえます。
地域主義が叫ばれながらも、原点に立ち返った実践論がなく、一村一品運動やイベントの羅列に終わり、その打開を迫られている現在、これら過去の郷土会・郷土研究の動きが、実践的な活動の広がりにつながっていれば、現在の地方のあり方も、農業に対する考え方も、相当よい方向に変わっていたものと悔やまれてなりません。
ただ、新渡戸の郷土会、柳田の郷土研究が見いだした多くの人材が、全国各地で「郷土教育」を実践し、いま再び、彼らの実践教育の軌跡が評価されつつあるということは、私たちにとって1つの励みでもあります。
|  田園を勇気づけた人々
田園を勇気づけた人々 田園を勇気づけた人々
田園を勇気づけた人々 早すぎた田園主義者「宮沢賢治」と「松田甚次郎」
早すぎた田園主義者「宮沢賢治」と「松田甚次郎」 田園散策のナチュラリスト「H・D・ソロー」
田園散策のナチュラリスト「H・D・ソロー」 はるかなる先見者「ウィリアム・モリス」
はるかなる先見者「ウィリアム・モリス」 郷土のエネルギー発現を目ざした「新渡戸稲造」と「柳田国男」
郷土のエネルギー発現を目ざした「新渡戸稲造」と「柳田国男」 風土の力に光をあてた「ラッツェル」と「三沢勝衛」
風土の力に光をあてた「ラッツェル」と「三沢勝衛」 みちのくの鳥のファーブル「仁部富之助」
みちのくの鳥のファーブル「仁部富之助」 田園の魅力を生涯追求した「天野藤男」
田園の魅力を生涯追求した「天野藤男」 消えゆく田園風景を描き続けた「コンスタブル」と「大下藤次郎」
消えゆく田園風景を描き続けた「コンスタブル」と「大下藤次郎」![[戻る]](back.gif)
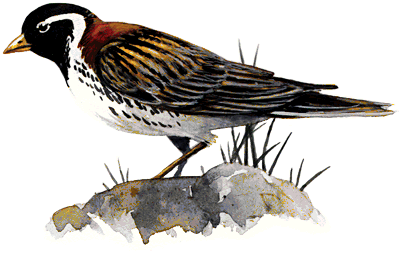 ドイツのメーザーは荒廃する村落を救うべく村落の理想像を探り、ヘルダーは田園の風物や民俗の意義を強調し、風土の思想を提唱しました。
ドイツのメーザーは荒廃する村落を救うべく村落の理想像を探り、ヘルダーは田園の風物や民俗の意義を強調し、風土の思想を提唱しました。